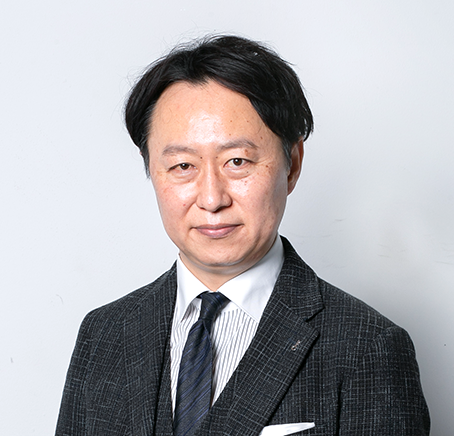―山本幡男 ラーゲリ(収容所)からの遺書より
今週の「言葉」は、先の大戦でソビエト軍によってシベリアに抑留され、愛する家族のもとに二度と帰ることが叶わなかったある日本人が4人の子どもたちに綴った遺書にある言葉です。この遺書の日付は1954年7月2日とあります。故郷や家族のもとに帰ることがなかった数々の遺書からは、当時の日本人の教養の深さ、今は失われつつある人生観、死生観、そして道徳観の深み、要するに人間としての共通規範とは何だったのか、そのことを教えられます。山本幡男さんとその家族、ラーゲリ(収容所)でのエピソードは、二宮和也さん主演で映画化もされ、この平和な世に再び脚光を浴びたことは記憶に新しいところです。
ポール・クローデルという、戦前に駐日大使を務めたフランス人がいます。彼は大正10年(1921年)から昭和2年(1927年)まで駐日大使を務めた人で、その経験から日本と日本人を深く知る人でした。その彼が戦中である昭和18(1943)年、敵国でもある日本及び日本人に対して、本国フランスのパリでスピーチした内容が残されています。
「私がどうしても滅びてほしくない一つの民族があります。それは日本人です。あれほど古い文明をそのままに今に伝えている民族は他にありません。日本の近代における発展、それは大変目覚しいけれども、私にとっては不思議ではありません。日本は太古から文明を積み重ねてきたからこそ、明治になって急に欧米の文化を輸入しても発展したのです。どの民族もこれだけの急な発展をするだけの資格はありません。しかし、日本にはその資格があるのです。古くから文明を積み上げてきたからこそ資格があるのです。」
そして最後にこう付け加えました。「彼らは貧しい。しかし、高貴である」
山本幡男さんは4人の子どもたちに、
「君たちに会へずに死ぬることが一番悲しい。成長した姿が、写真ではなく、実際に一目みたかった。お母さんよりも、モジミよりも、私の夢には君たちの姿が多く現れた。それも幼かった日の姿で……あゝ何といふ可愛い子供の時代!
君たちを幸福にするために、一日も早く帰国したいと思ってゐたが、到頭永久に別れねばならなくなったことは、何といっても残念だ。第一、君たちに対してまことに済まないと思ふ。」と語りかけたうえで次のような遺訓を残します。
要約すると、
・辛いことがあっても、高貴な日本民族の一人として生まれたことに感謝することを忘れてはいけない
・人道主義を以って、東洋と西洋を融合し、世界文化の再建に尽くすのが日本人の歴史的使命であることを忘れないでほしい
・どんなに辛い日があろうとも、人類の文化創造に参加し、人類の幸福を増進するという進歩的な思想を忘れないでほしい
・偏頗で矯激な思想に迷ってはならない。どこまでも真面目な、人道に基く自由、博愛、幸福、正義の道を進んでほしい
・最後に勝つものは道義であり、誠であり、まごころであるから、友だちと交際する場合にも、社会的に活動する場合にも、生活のあらゆる部面において、この言葉を忘れてはならないぞ
・人の世話にはつとめてならず、人に対する世話は進んでしなさい。但し、無意味な虚栄はよしなさい。人間は結局自分一人の他に頼るべきものが無いという覚悟で、強い能力のある人間になってほしい
・精神も肉体も鍛へて、健康にすること。強くなれ。自覚ある立派な人間になれ
極寒の地から、俘虜の戦友たちから残された遺書、ここに示されている人間観には、公共心と自助・共助・公助の真のあり方を教えられます。現代の義務を果たす前に権利ばかり主張する人々、勤勉さを忘れつつある日本の現状に、こうした教育を官民総出で復古できるならば、未来は力強く、そして一人ひとりが生きることへの意味を感じられる世に再びなることを期待して、このことを傍観せず自らの使命として山本さんに誓い、感謝するところです。
もうすぐ、山本さんがこの遺書を書いた7月です。