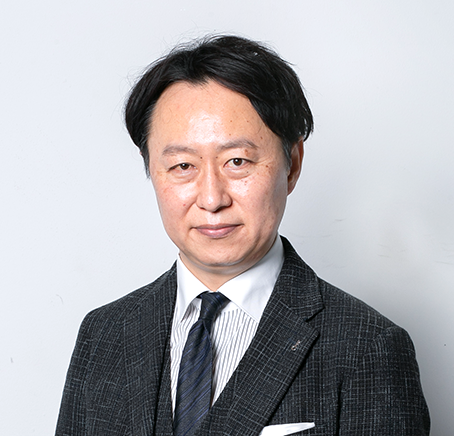◆人手不足倒産が加速している
今週の日経新聞の記事でも取り上げられていましたが、東京商工リサーチが10日に発表した1月の企業倒産(負債額1000万円以上)は840件と前年同月比19.8%増え、1月で800件を超えるのは2014年以来11年ぶりとのこと。そのうち「人手不足」が理由の倒産は3.2倍であったとのことです。中でも労働集約型産業での人手不足倒産が多く、例えば建設業においては24%増の倒産件数となったとのことです。
◆なぜ経営の最重要資本である「人」を確保できないのか
ちょうど10年ほど前に、会社の存続を脅かす「すでに起こっている」危機として、最も私が取り上げていたことに、人口動態の未来予測があります。生産年齢人口が減っていくことにより人材の確保がこれまで通りには決して行かないことは多くの経営者は認識していたことと思いますが、その実態は何十年も前にドラッカー先生が示したように甘いものでした。ドラッカーは『マネジメント』の中で「本当の資源は一つしかない。ひとである」(同書 第4章)と語りました。一方こうも語ります。
「経営者は『人材こそわれわれの最大の資源である』と好んで口にする。組織によって何か実質的な違いがあるとすれば、それは人材がどれだけの成果をあげるかだけだ。この分かりきった真実を、経営者たちはしきりに述べ立てる。」
「あらゆる経営資源のなかで最も活用度が低いのが人材であり、人材の可能性はほとんど埋もれたまま仕事に活かされていない。」
(出典:P.F.ドラッカー著、有賀裕子訳『マネジメント 務め、責任、実践』日経BP社)
ドラッカー先生が示す経営の原理原則のなかに「マネジメント3つの役割」があります。すなわち、
①組織の具体的な目的と使命を果たす
②業務の生産性を上げ、働き手に達成感を得させる※
③社会への影響に対処し、社会的責任を果たす
※原著では“Productive Work and Worker Achievement”です。「働く人を活かす」、とも訳されます。
「人手不足」で悩む会社はほぼ例外なくマネジメントの役割②に該当する人を活かすことに関心の低い会社と言えます。またほぼイコールで①が決定的に弱い。悲しいほどに弱いケースが多く感じられます。弱いとは具体的に言えば「理念・目的」なき作業を日々させてしまっている会社です。さらに具体的に実態を表現すれば、「公欲(世のため人のための貢献)」ではなく「私欲(金のため)」が優先されて意識づけられている会社のことです。つまり先義後利が本末転倒しているということです。公欲の人々が集う会社には人が集まり、私欲の会社からは人が去っていきます。当然の理です。
一方、「人材こそわれわれの最大の資源である」との経営思想を言行一致させている会社はこの時代にあってもなお人が辞めずに事業の成長とともに増え続けています。
10年以上お仕事をさせて頂いている総合建設会社様は、10年前は若手社員の離職率が50%を超える状態でしたが、直近3年間で入社した若手社員の離職率は1.8%にまで下がっています(2022年度・23年度・24年度に新卒入社した54名の3年以内離職率)。20年近く日本では3年3割というのが離職率の実態値ですが異様な低さです。この建設会社様で10年前に徹底的な現場社員のヒアリング調査をしたことがあります。そこで分かったことは、入社3年を超えても活躍し続ける社員の共通点は、若手時代に次のような共通点がありました。
・(年代問わず)仕事を任せ、コミュニケーション※を重視し、丁寧に指導する上司に恵まれること
・仕事の意味、全体像を掴むこと
の上記2点が主に挙げられます。
※コミュニケーションという言葉も非常に曖昧な言葉ですが、具体的には「気軽に相談ができること」「連絡と報告が密になされていること」「場合によっては上司から先に相談をしている(どういう風に仕事進めてみたい?など)」といった部下の状況に合わせた丁寧な指導スタイルを取っていることです。これはシチュエーショナル・リーダーシップ(SL)として有名なスタイルです。またこの会社様ではコミュニケーションをさらに戦略的に人財育成を促進するために報連相のほかに、「対話」「議論(衆知を集める)」「振り返り」もその後強化しました。
一方で3年以内に辞めてしまう若手社員(一部中堅も含む)の共通点としていくつかあるのですが、その一つに「仕事の全体像が見えず、それゆえに達成感を感じられない」というものがありました。まさにマネジメントの役割②“Productive Work and Worker Achievement”に該当します。つまり、出口の見えない暗闇の中で不安なまま仕事をさせていたことになるわけです。
なぜ経営の最重要資本である「人」を確保できないのか、の結論は、
「マネジメント」を管理することと勘違いし、正しくマネジメントを理解した経営者・マネジャーがいないため、的外れな自己流の人材育成が蔓延り、“マネジメント”が存在していないことです。これは日本の中小企業を中心に長期的な存在価値に関わる課題が故に、喫緊の着手を求める重要課題です。
先人・先輩が我々を育んでくれたように、自分自身も後輩・部下を大切に育んでいきたい。企業文化としてのそのような精神のバトンを経営で大切にしていますか。この問いが、人材不足で悩む多くのリーダーにとって良い転換点となれば、この上ない喜びです。