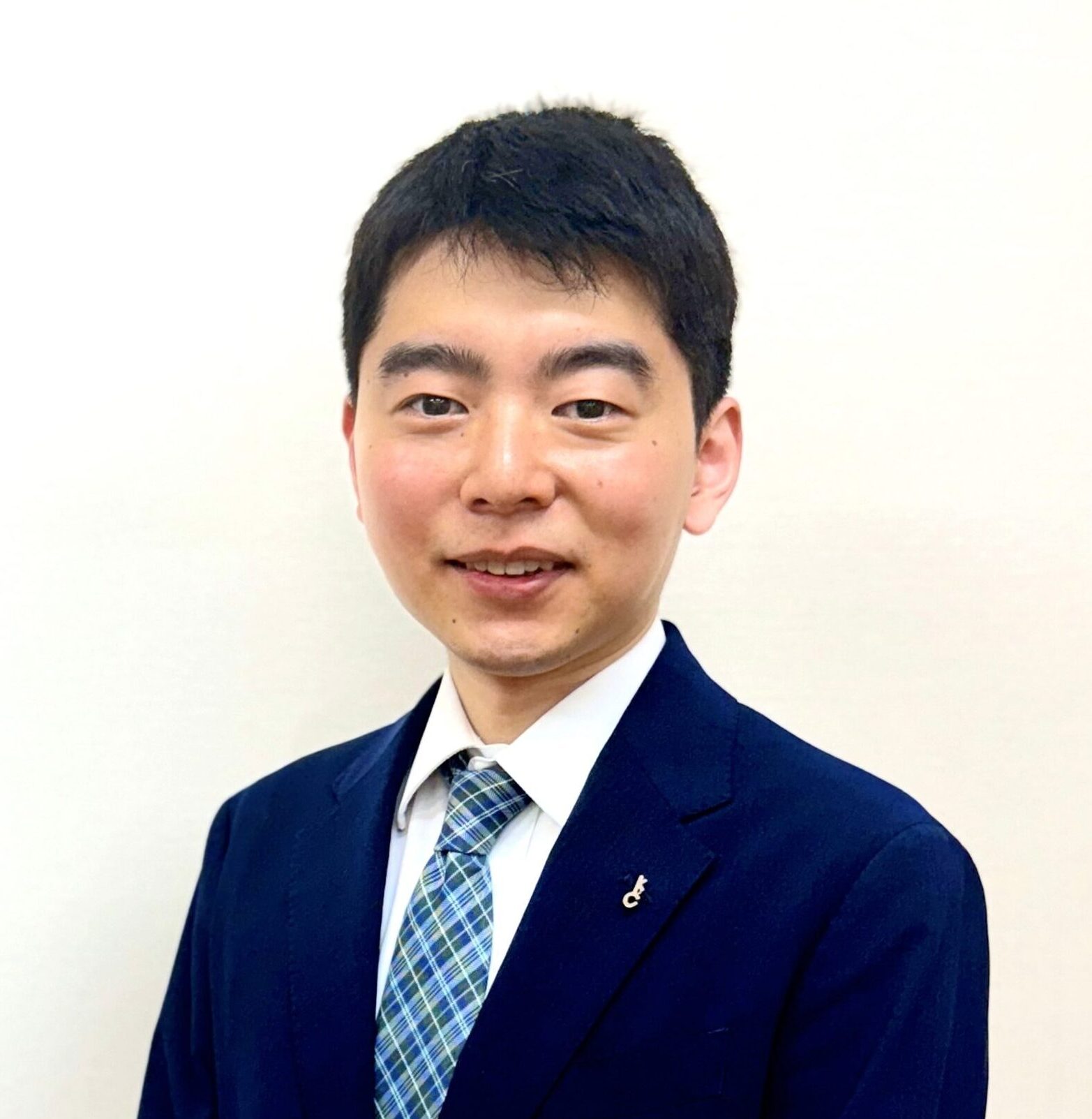米トランプ大統領とウクライナのゼレンスキー大統領が2月末に面会し、口論の末に決裂した、というニュースをご覧になった方は多いと思います。ウクライナの支援はあくまでディール(取引)であり、アメリカに直接的な見返りがなければ行わない、というトランプ政権の姿勢を改めて示すものでした。また同政権は、対立する中国のみならず、隣国のカナダやメキシコに追加関税を課し、今後はそれ以外の国も含めたアルミや鉄鋼、自動車等への関税、国ごとの相互関税なども検討しています。
米連邦政府に目を向けると、マスク氏の率いる政府効率化省(DOGE)により、職員や組織の大幅なリストラが実行されつつあるようです。国民の注目や支持を集めるため、既存の官僚機構を攻撃するやり方は、毛沢東の「文化大革命」に類似しているとの見方もあります(2/25日経新聞朝刊5面「オピニオン」欄)。効率化の次元を超えたマスク氏の施策が実行されれば、文革の10年間に中国の国力が停滞したように、政府機能の弱体化に陥るおそれがあるのです。
こうしたアメリカの外交・内政の姿勢が続けば、日欧など同盟国・同志国を含む世界各国との協調が弱まり、経済面では過度な保護主義がアメリカの産業競争力を低下させる懸念があります。また政府機能も一度低下・喪失したものを挽回するのは容易ではないでしょう。強硬な姿勢を見せるトランプ政権ですが、4年間の政権運営次第では、かえってアメリカのプレゼンスを低下させ、強権国家の付け入る隙を与えかねないのではないかと危惧します。
一方で、アメリカ経済は今のところ力強く、GDPは11四半期連続のプラス成長を記録しています。トランプ政権は「アメリカファースト」を唱えており、同政権の掲げる諸政策は、短期的には米経済にプラスに作用しうると考えます。しかし、上記のようなプレゼンス低下やそれに伴う世界情勢の不安定化が現実となれば、基軸通貨であるドルの信認低下や、急激な円高などのショックが発生するかもしれません。また米経済が低迷すると、日本全体の景気にも大きな影響をもたらす事態は避けられません。
目下では強い経済が続くアメリカですが、世界情勢を含めて変調の兆しがないかどうか、日々意識的に見ておくことが必要だと思います。外部環境はコントロールできませんが、新聞やニュース等を通じ常にアンテナを高くし、発生しうるリスクに備えることが重要だと考えます。