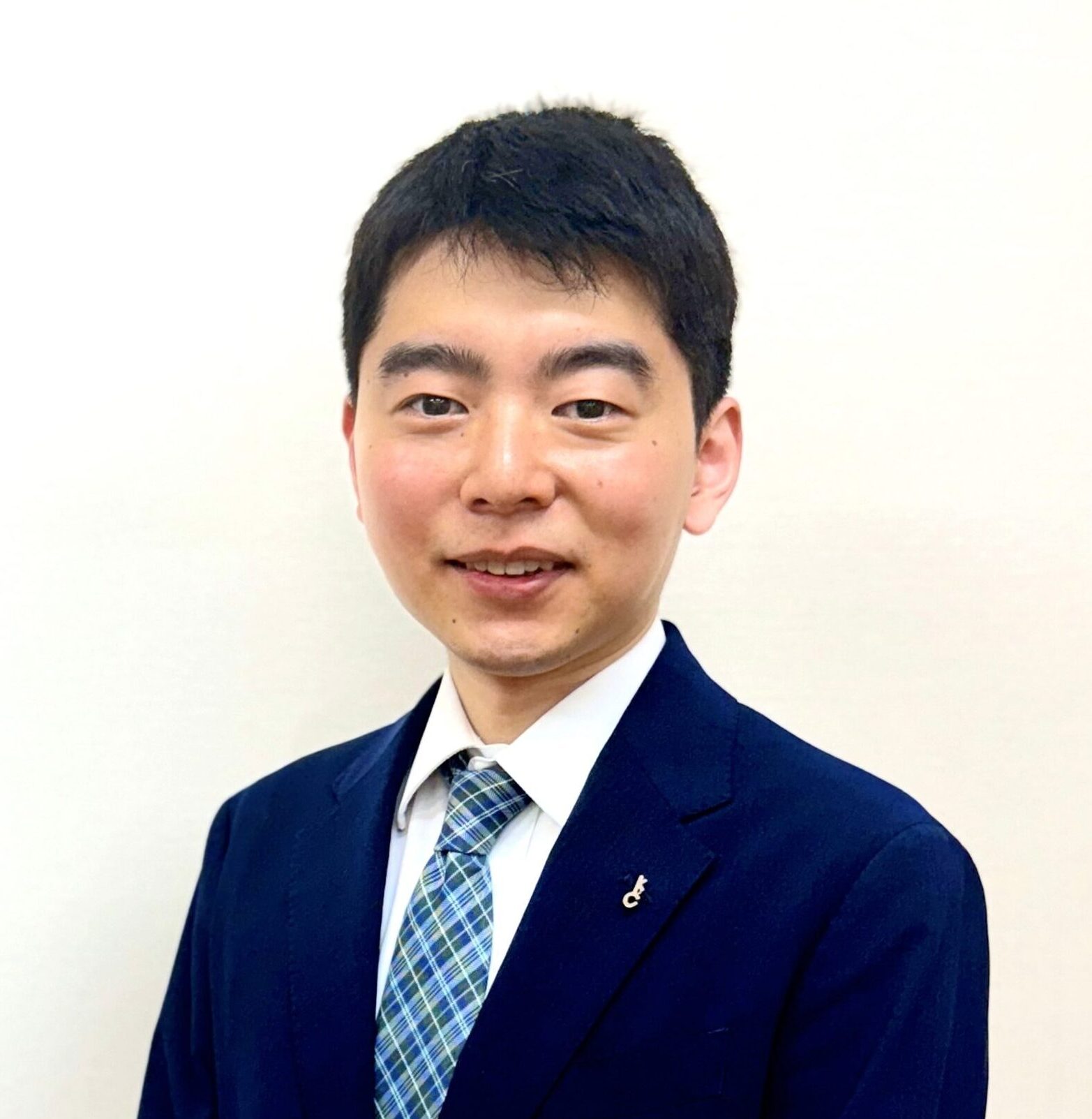3/23(日)付の日経新聞に「日本、気がつけばG7首位のインフレ 「普通」の国に」という見出しの記事が掲載されました。総務省の発表では、2月の消費者物価指数の上昇率(前年同月比)は米国が2.8%、ドイツが2.3%、フランスが0.8%だったのに対し、日本は3.7%(総合)と頭一つ抜けており、主要7か国(G7)中で最も高い水準となっていると報じています。
記事では、経済協力開発機構(OECD)が公表したインフレ見通しについても言及し、日本の相対的に高い水準のインフレ率は、2025年から26年にかけ継続する見通しで、「一時的、瞬間風速とは言えない」と指摘しています。一般的に「インフレ率」といえば、消費者物価指数(最終消費者の購入する財・サービスの価格指数)の変動率を指します。その消費者物価に大きな影響をおよぼすと考えられる企業物価指数は、2025年2月に前年同月比+4.0%の水準に達しています。前述の通り消費者物価指数は+3.7%(生鮮品を除く総合で+3.0%)ですから、企業が仕入価格の上昇分を最終価格にまで反映しきれておらず、今後も消費者物価上昇の圧力が継続することが予想されます。
なぜ、日本がG7で最高のインフレ率になったのでしょうか。一言で言えば、他国と比べて「周回遅れ」になっているからです。
アメリカでは、コロナ禍を経たリベンジ消費や、ロシアのウクライナ侵攻によるエネルギー価格高騰等の影響で、2022年には一時9%を超えるインフレ率を記録しました。それに呼応し、2023年には政策金利が5.25-5.50%の水準まで引き上げられました。一般に、金利を上げると借入は減り、消費や投資が減る方向に働くことから、景気は抑制され、インフレ率も低下します。そのため2023年1月に6.4%あったインフレ率は、24年1月には3.1%にまで低下しました。これを受け、現在アメリカは政策金利を引き下げつつあり、現在は4.25-4.50%となっています。ユーロ圏も同じく、2023年に金利を4.50%まで引き上げたのち、現在2.65%まで引き下げています。
一方の日本はどうでしょうか。2023年1月に4.2%(生鮮除く総合)のインフレ率を記録したものの、政策金利はマイナスのまま据え置かれ、マイナス金利が解除されたのは2024年に入ってからでした。その後も徐々に利上げが進み、現在の誘導目標は0.5%となっていますが、目下の3%台のインフレ率には遠く届いていない状況です。他国が金利を引き上げたのち、今は利下げのフェーズに入っている中、日本は未だ金利を引き上げる途上であり、その意味で「周回遅れ」といえるのです。
上記のように、①現在のインフレ水準は短期間では沈静化しないと考えられる ②日本は周回遅れで金利を上げ始めているが、未だ低い水準である ここから何が示唆されるでしょうか。それは、金利はまだ上昇する余地があるということだと考えます。
加えて、米トランプ政権は円安を批判する発言を行っているため、もし日本が円高に誘導するのであれば、なおさら利上げの機運は高まるでしょう。利上げの最高到達点(ターミナルレート)がどの水準になるのかは分かりませんが、1%以上との見方も多く、それに伴って借入金利も上昇することになります。「金利ある世界」に耐えうる充分な収益性がなければ、利払い負担は大きくなり、また銀行からの借入自体難しくなる可能性もあります。そのような意味からも、将来の金利上昇を見据え、財務的な安全性や収益性を高めておくことが必要と考えます。