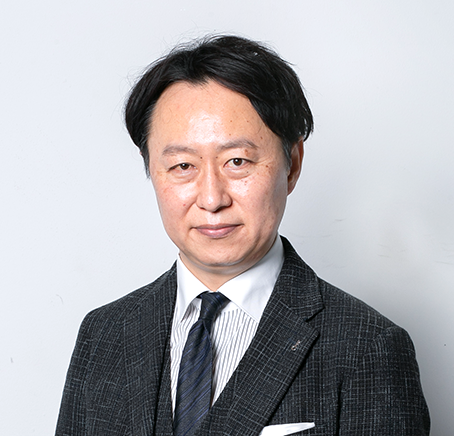ー新渡戸稲造『武士道』「第五章 仁・惻隠の心」より
今週の「言葉」は、20世紀の初めに日本及び日本人論を世界に広めた三冊(内村鑑三『代表的日本人』・岡倉天心『茶の本』とともに)の一つ、新渡戸稲造の『武士道』からの引用です。
1868年(明治元年)、江戸城が無血開城し明治のご一新を敢行した日本は、欧米列強に比肩すべくグローバル化の波にさらされていました。その明治維新からたったの30年余で日本は日清戦争・日露戦争を経て、世界の列強と肩を並べる初の有色人種の国として海外から注目を集めることになりました。そしてそれは同時に、戦争好きの野蛮な民族であるとの偏見も伴っていたのです。そこで正しく日本及び日本人を世界に理解してもらおうと1900年を前後として日本を代表する三人の文化人が欧米人に向けて英語等で日本を紹介する本を出したのでした。
その一冊がこの『武士道』です。今でも海外のリーダーが日本及び日本人を認知している土台にはこの三冊がその土台になっていることは珍しいことではありません。一方、日本で生まれ育った日本人そのものが本書のような教養を備えていることは、逆に稀有なものとなっています。
因みに『武士道』は英語のみならず、ドイツ語、フランス語、ポーランド語、ロシア語、イタリア語など多くの国で翻訳されるベストセラーとなっています。当時、第26代アメリカ大統領であったセオドア・ルーズベルトは一夜のうちに本書を読破し、感動のあまり30冊を世界中の要人に送って一読を薦め、また自身の子供たちにも読み聞かせたそうです。
仁・惻隠の心とは
ここ数日も、悲しい事件が朝のニュースから流れてきます。「仁」とは『論語』における最高の徳目、「惻隠」とは『孟子』において「仁」の基とされた人間に不可欠且つ誰もが持っているはずの心の核です。
「仁」の字を眺めれば、二人の人とも読めます。つまり、私たちが生きるこの社会、組織、そして家族というものは、一人では成立せず、必ず二人以上の人間の関係性から成り立ちます。その人間の一方に思いやりや優しさ、そして愛情がなければすべては成り立ちません。ゆえに人間道徳の根本として教えられ、自らその徳目を修めようとしてきたはずでした。
「惻隠」とは困っている人をみて憐みの心を持つことをいいます。江戸時代~戦前であれば4歳くらいからこの心を育むことをしたものです(多くの偉人の回想録などでも書かれています)。江戸時代には15歳になるまでに五常(仁義礼智信)を修めることを目標に、4歳ごろから「四端教育」として惻隠の情を幼年教育の中心に据えました。
幕末に吉田松陰先生が著した『武教全書講録』には武士道のあり方として次のように教えています。
「先ず士道と云ふは、無礼無法、粗暴狂悖の偏武にても済まず、記誦詞章、浮華文柔の編文にても済まず、真武真文を学び、身を修め心を正しうして、国を治め天下を平らかにすること、是れ士道なり。」
後半部分だけ現代語にすれば、「真の武と真の文を学び、それによって身を修め、心を常に正しくして、よって国を治め天下を平和にすること。それが私たちが目指す武士道というものだ」となります。この修身の過程を現代の教育や経営の土台に取り戻したいものです。