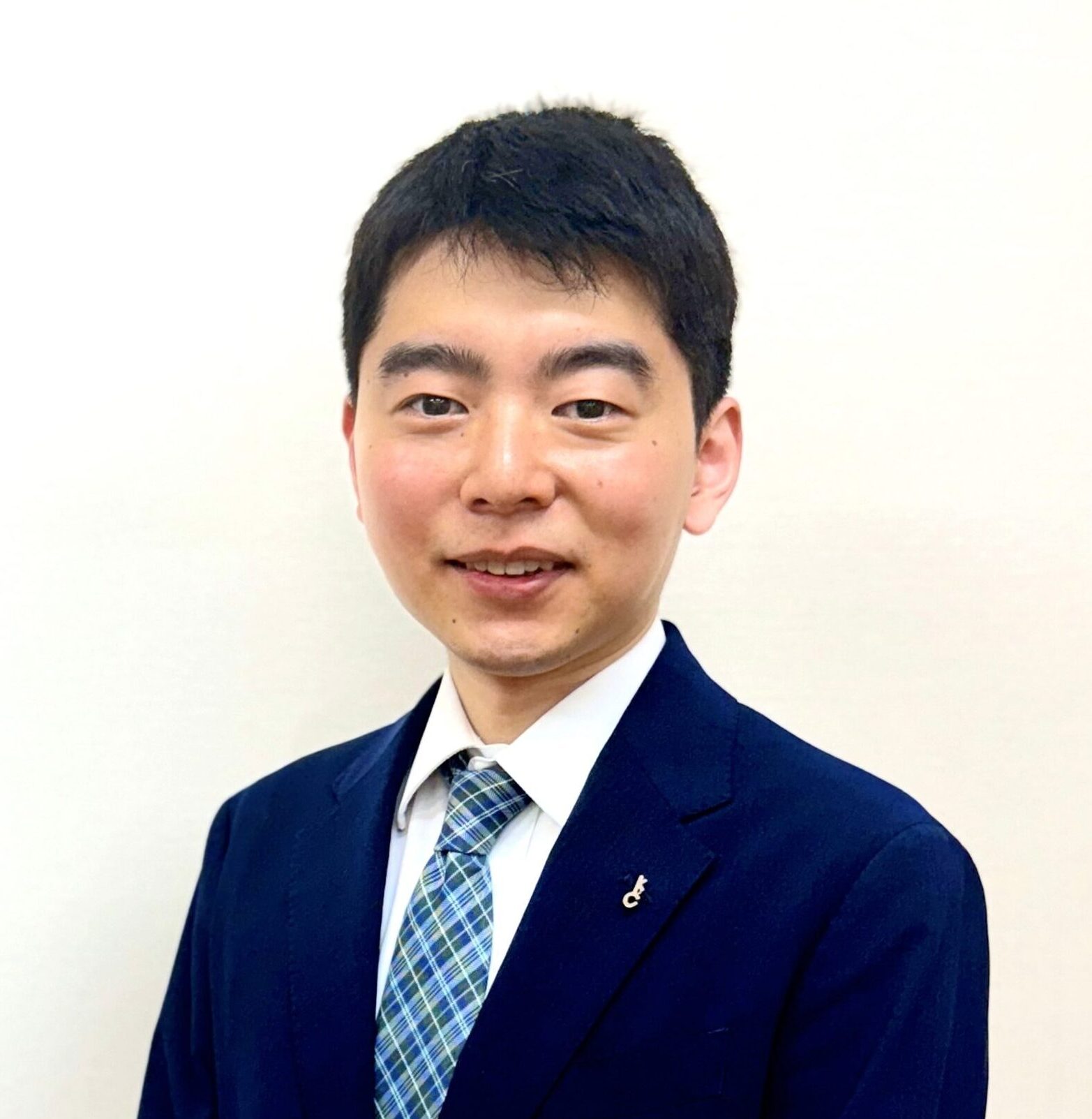4月に放送された「NHKスペシャル 未完のバトン」という番組で、財務省の国債発行チームが日本国債の円滑な消化のため、様々な取り組みを行う様子が放送されており、興味深く視聴しました。中でも印象的だったのが、中東の投資家に日本国債購入の打診をしているシーンでした。投資家たちは、「ほかの先進国と比べた日本の債務残高対GDP比をどう分析しているか?」「債務残高対GDP比が今後安定するもしくは下がるという見通しを示してください」「(選挙で与党が過半数割れし)ある野党の党首はさらなる景気刺激策を求めているようだが(どう考えるのか)?」と、日本の財政の持続性について、単刀直入に指摘していたのです。
そうした海外投資家の懸念をよそに、参院選を見据え多くの党が減税策を唱えていますが、市場は敏感に反応しています。日本の超長期国債(期間が10年を超える国債)の金利が上昇しているのです。新発30年債は5月15日に25年ぶりの水準となる2.98%、40年債は5月7日に過去最高となる3.25%を記録しています。5月9日付の日経新聞(朝刊10面)によると、超長期国債においては、生保などの国内勢に代わり、足元では売買の約5割を海外の投資家が占めると報じられています。国債は価格が下がる(売られる)と金利は上昇しますので、超長期国債の金利上昇は、日本の長期的な財政悪化を懸念するシグナルと捉えられるのです。
これに類似した事例として、2022年の「トラス・ショック」を覚えていらっしゃる方は多いと思います。当時の英国のトラス首相が、歳出削減を伴わない大幅減税策を打ち出したことで、英国の財政に対する市場の不安が高まり、国債が売られ長期金利が急騰したのです。住宅ローン金利の上昇など社会的混乱が生じ、結果として首相は在任わずか1カ月半で退陣することとなりました。
日本においても同様の事象が起こらないとは限りません。発行残高の対GDP比が約250%と先進国で最悪の水準にある中、これまでは「国債は大半が国内で消化されているから問題ない」と言えたかもしれません。しかし、少なくとも超長期国債については、今や売買の5割が海外勢であり、シビアに日本の財政の持続性を見ているのです。
国としての信認を失うとどうなるか、は歴史がそれを示しています。お金(日本なら日本円)の信用がなくなることで、すさまじいインフレが国全体を襲うのです。5%や10%どころではありません。例えば第1次世界大戦で敗戦国となったドイツ(ワイマール共和国)では、物価水準が1兆倍の水準にまで跳ね上がり、国民生活は大きく傷つき、大衆の不満はのちにナチス政権を生み出すこととなったのです。
冒頭の番組で、財務省の担当者は、日本の経済基盤の強さなどを説明し理解を求めていました。しかし、もし政治が短期的な票の確保のために財源なきバラマキ策に走れば、いくら説明しても日本国債を買ってくれる投資家はいなくなるでしょう。日本の財政の持続可能性を真剣にみているのは海外勢だけだった、というような本末転倒な状況を起こさないためにも、我々自身が長期的な視点を持って、この国の未来を考えるべきではないかと思います。