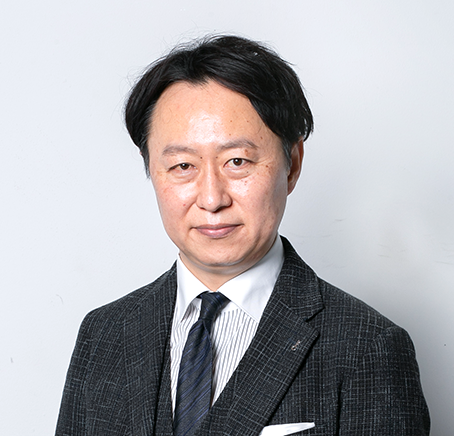(弊社所属のコンサルタントによる長編コラム「KC文集2023」掲載記事)
■一人でも多くの社会人が「良い会社」を求めることが社会をより良くする
私たちが地球上で生まれ、自然の恵みを受けながら平和を希求する世界の一員として国家に属し、家という社会の最小単位において人間として育まれ、やがて成人に至るまでに独立心を得、自ら修練を重ねて社会のなかで自立し、自らその社会のより良い発展に責任をもち、そして自己実現の先に社会に貢献することは、社会人として誰もが通るべき人間の道です。
現代を生きる私たちは自ずと社会に属し、家の外にある何らかの社会の公器である組織(多くは会社)に属し、仕事を通じて職業人としての成長、そして人間としての成長をし、一人では成し得ない成果をあげることで社会に貢献することが叶います。その多くの人が所属している「会社」という組織に於いて成果をあげるために私たちが知っておかなければならないことがあります。すなわち先人が既にその身を以って失敗と成功を繰り返したことで遺してくれた「原理原則」「正しい考え方」を知り、自分のものにすることです。そのために我々が学ぶことは真に知られるべきこと、つまり古典とされるものに多く遺されています。しかし、この学ぶということには一つの決定的な何かが必要です。
それは言うなれば「自らを突き動かす熱源」です。人間としての行動の熱源とは何か。それは現実への違和感、人間として生まれたことの恍惚や劣等感など、私の観るところ様々です。ただ一つ、「ありたい姿」を個人として希求し、或いは実践を通じて得た教訓としての「あるべき姿」を自らに内在していることが熱源をもつ絶対条件です。先ほども述べた「原理原則」「正しい考え方」を知り実践すると湧いて出てくる場合もあります。実践によってその本質を知り感動するからです。私の場合、仕事人生を通じて先人の教えに大いに感動する、そうした情動が私の熱源を得るプロセスにあったのは確かです。
この熱源を生み出すギャップ、すなわち現実とありたい姿から生み出される違和感や厳しい現実直視は人間としての哲学を伴います。思想信条が無い仕事や経営は舵なき船であり、暗夜に一燈を提げずにただ不安げに闇を歩くのと似ています。哲学とは究極的に「何のために生きるのか」を自らに問うことです。その問いから生み出された一つのシンプルな経営及び仕事の哲学、それが「良い仕事」を通じて「良い会社」を創ることです。弊社小宮の『社長の心得』の次の一言に触れたとき、それが実践の中でもがき苦しむ私の一燈となりました。
すなわち「良い会社とは何かを知り、常に意識していくことが、良い会社にする第一歩である。」との一文。さらにその良い会社とは何か。それは次の3つの条件から成ります。
1.お客さまに喜ばれる商品・サービスを提供して社会に貢献する会社
2.働く人が幸せな会社
3.高収益の会社
つまり、人間として生まれ、現代に生きる上で、この3つの実践を通じて成果をあげること、このことが世に1社でも多く「良い会社」を増やして死ぬこととの自らの使命を知ることになったのでした。この理想を知ったとき、私の眼前には限りある人生の時間をこの良いことに使われていない、謂い方を変えれば、目的無き手段、手段のための手段、保身のための無駄、そして思想信条や人間への愛情なきマネジメント(いま思えばマネジメントというよりもただの“管理”)が横行していました。その現実を直視し、自らが所属する会社やその上司や他者に依存することなく、自らの正しい努力と実践によってのみ、目の前の現実をより良い場所に出来ると思うようになりました。
元来が未熟な人間ゆえにまだまだ困難な道ですが、その一燈を信じて歩むほかないとの覚悟を決めたのは30代も後半。
あとどれほどの人生の時間が残されているかもわからない、その中で私の役割は「良い会社」を希求するリーダーの育成という仕事に見出しました。
20代、奇蹟の連続によって私はフルコミッションの営業の世界に飛び込み、そこで30人~60人の人生を預かる営業所長、支店長という役割をいただき、期せずして営業のみならずマネジメントの道に放り出されました。
当時は何も知らないまま、多くの人の人生を左右する立場にあったこと、いまでは身震いしますが、失敗を重ね、やがて一人ひとりの人生と向き合うことの重要性を知り、その営みとしてコミュニケーションを重ね(いまでいう1on1)、一人ひとりとその集合体である組織が成果をあげるには理念(なんのために個々で働いているのかの羅針盤)とプロセスが必要であることを実践の中で見出し、みんなのお陰で一定の成果をあげることができました。
その経験財産は、30代、大企業やそのグループ会社で働く中で決して誰でも持っているわけではない、特有の強みを私に与えてくれていたことを知りました。それは営業力と人財育成への強い“関心”でした。人財育成の根本は、“人間は自ら育つもの”であるがゆえに、私はその刺激物になって支えるしかできない。教化は出来ても成長は自らの修養によってするものであることを感じ取っていたがゆえに、その者に関わる者、組織に於いては特に影響力の大きいリーダーたる者の人間への“関心”が決定的に重要なのです。
私たちの世代(私は昭和50年生まれ)は、氷河期世代、或いは失われた世代(ロストジェネレーション)と言われてきました。
しかし私は元々失うものがあったわけではなく、常に何か満ち足りなさを抱えながら生きていました。ゆえに、「何が失われた」のかよくわからないまま若い時分を生きていたといえます。権限も地位も、報酬も有形資産もさしてそのようなものは無く、守るべきものと言えば自分の生活くらいでしたが、そうした生き方に何か物足りなさを感じていた程度です。
しかし、30代半ばを過ぎ、なぜこんなに自分も周囲も働いているのに、或いは情報技術や自然科学は発展しているのに、世の中や人々の人生は何も発展していないように見えるのか、むしろ人々の仕事への熱意、アニマルスピリッツのような生きること、働くことへの何かしらの渇望、互いの人間に対する愛情など、もしかすると退化しているのではないか、そう感じるようになったのでした。
この違和感が、「良い会社」を一社でも増やしたいと思い至る背景にあったのも確かなことです。
新規事業のリーダーを務めるに至って、仕事にもまれる中でそのマネジメントの必要性から新たに時間を割き、社会科学としての人間学、経営学、歴史学或いは碩学巨人の肩に乗って実践のマネジメントを学ぶ機会を増やしていくうちに、今さらニュートンの理論を持ち出して研究する人がいないように自然科学と違って人間に関わる社会科学の分野ではむしろ効率性、生産性を社会や組織が求めすぎるとやがて合成の誤謬、手段の目的化、そして私が最も目の当たりにした組織と個人の部分最適の追求と“追及”が横行し全体として退化していく過程を観ました。結果、短期的な目標のためだけに仕事への人々の意識が埋没され単なる作業となり、長期的な価値や唯心論的な価値を減退させてきたプロセスを観てきました。
そうした意味で、本当にこの間に“失われた”のは結果としての経済的低迷のみならず、むしろ大きいのは人々の精神的側面の方ではなかったかと確信するようになりました。この流れを変えるのは私たち現役世代の責務であり、組織に大きな影響を与えるリーダーのあり方を変えることこそ、次世代の可愛い後進、子々孫々にもたらす恩恵とは何かを考え、長期的な視野に立って一意専心すべきことではないかと思っています。人間の為すあらゆる結果は「強く思うこと」、すなわち稲盛和夫さんが示してきてくれたように「心」から始まります。この心に立ち、私たちリーダーが今こそなすべき事を再確認すべきこと、集中して実践すべき事は何かを問いたいと思います。
■安岡正篤氏の憂いとリーダーが持つべき「思考の三原則」
我が国は戦後既に78年の経過を得ています。私たちはもう「戦後」でもありませんし、150年前に先人が為してくれたように新たな創造の時代に生きなければなりません。世界に貢献する国家であり、国民でなくてはなりません。しかしそのために我々がもう一度知っておかなければならないことは現実を正しく直視すること、そして誰が正しいのかではなく、何が正しいのかを学び直すことにあると信じます。そこで大変参考になるのが戦前・戦中・戦後を国家の最前線で指南してきた安岡正篤氏の慧眼および警句です。その著書『運命を創る』に次のような後世への強いメッセージが語られています。
「今日の日本の堕落、頽廃、意気地のなさ、こういう有様は昨日今日のことではない。非常に長い由来・因縁があるということを考えないと、これを直すことはできません。皆さんが今後起こってくる諸般の問題をお考えになるには、目先の問題をとらえた流行の皮相な理論では駄目でありまして、先程申したように、少なくも明治以来の思考の三原則によって徹底した考察をなさらないと正解を得られない。したがって、今後の真剣な対策も立たないということを私は信ずるのであります。」
(出典:安岡正篤『[新装版]運命を創る―人間学講話』プレジデント社、※傍線筆者)
この「明治以来の思考の三原則」とはすなわち何か。それは次の3つになります。
1.長期的に観察する(目先にとらわれないで、できるだけ長い目で観察する)
2.多面的、全面的に考察する(一面にとらわれない)
3.根本的に観察する(枝葉末節にとらわれない)
そしてこのことに加え、明治のご一新が革命にならずに世界史的にも格調高くに行われたことの根底には江戸時代の教学(人物と教養)にあると述べています。因みに江戸時代の教学とは、仏教・儒教・神道を統合した武士道や五常に代表される徳目(仁・義・礼・智・信)、更にはその教義を突き詰めた陽明学にある知行合一(知ったことは行え、との強烈な実践思想)による修養と実践のことです。平たく言えば人間学を先にし、西洋技術をその上に取り入れた日本人の和魂洋才のイノベーションの起こし方です。『大学』にある本学(人間学)を先にし、スキルはその後にする、との本末がしっかりあったということです。
この事は開国以降のビジョンを構想していた開明派、佐久間象山、横井小楠の書にも明らかです。
その実践部隊を形成したのは身分にかかわらず後の緒方洪庵先生、吉田松陰先生以下門下生、及び西郷南洲に代表される薩長を中心に諸藩の下級武士の面々でした。この事はピーター・ドラッカーが晩年に「明治のリーダーに学べ」とのメッセージを我々に遺したことにも符合します。
一方、その明治の正しいエネルギーも日露戦争を絶頂として明治もおいおい下り坂に至る(官僚組織、学歴主義、功利効率主義などによる頽廃)とも述べており、この事は戦後80年を迎えようとする現在にも似たものを個人的には感じます。いままさに、民間の私たちが独立心を起こして草莽崛起するならば、この思考の三原則に立ち返って修養し、経営やマネジメントを実践するほか無いと感じています。
つまり、改めて東洋哲学(輪を以って尊しとする日本哲学に昇華)を根本にした正しい考え方に基づいて未来を切り拓くことが求められているのです。この思考の三原則に立ち返り、今後の中堅・中小企業の発展に不可欠と考えるミドル(中堅層・中間管理職)も含んだリーダーのあり方、及びその実践についてどうあるべきか、その思考と実践をこれまでのリーダー育成の現場実態も観察しながら敷衍します。
■中堅・中小企業におけるリーダーの枯渇
私は過去5年間で約1000人の経営幹部、経営幹部候補の皆さんとその成長の場を共にさせて頂いてきました。
年間200名前後の所謂「長」がつく役職の方々が中心です。年齢は様々です(リーダーであることは自覚によるものですので役職、年齢は関係ないことは昨年の本文集で述べました)。
一方、若い世代の方々が自律して、各々がリーダーを志す人財の育成も数社様でご支援しております。この取り組みの中で分かってきたこととして、成果をあげるリーダーと、そうではないリーダーの差はどのような在り方にあるのか、その本質が改めて見えてきました。
無論、人間に関わることですので、その人柄、経歴、専門分野等は様々で、決して一様ではありません。
ただ、“目に見えない”部分、つまり心の持ち方、その作用、そしてその心を支える基本的な考え方、更には自らを突き動かす熱源にはある一定の共通点があると考えています。また1000人次世代を担うリーダー候補、経営者候補の方々と向き合ったとしても、実際にマネジメントにおいて成果をあげ、次世代の重責を担える人物になるのは、1割~2割です。多い企業では年間リーダー養成のプログラムに100時間以上取り組みます。その前後には課題にも取り組んでもらっています。
しかし、その学習と実践の“量が質に転嫁”するのは3割も存在しないという事実があります。
一方、こうしたリーダー育成の取り組みを日常業務以外に取り組んでいない企業では、自然とリーダーが正しく育っているという状況はほぼ皆無です。目の前の仕事、目の前の売り上げをあげる、或いは社内の調整弁となって短期的な活躍が出来る人財は、我が国の中小企業に豊富です。ただ残念なことにリーダーがいません。
ここで私が語るリーダーとは、どのような存在のことか。人間に関わることですので、自然科学のように唯物的な定義はできませんが、時代の要請とともに、いまと未来の世の中をより良くするためにあるべきリーダー像とは下記のような人物を想起しています(基本的な私のスタンスとしてリーダー像は自らの強みを活かして自らが築き上げるものだという考えですので、“想起”としています)。
1.個人的な野心ではなく、世の中をより良くしたいとの高い志を内に秘めている人物
2.人と仕事において、短期的な利益のために長期的な価値を見失わない人物
3.お金や目に見える価値よりも、人間としての正しい道を実践しようと努力を積み続ける人物
4.すべては自らの受けた恩恵に感謝し、次世代の人を育てることにその報恩を実践する人物
この類型の根底には、松下幸之助さんや稲盛和夫さんの経営哲学、そして経営の古典、ピーター・ドラッカーの『経営者の条件』や『マネジメント』に示されたリーダー(本書ではエグゼクティブと表現される立場にある者)の使命、すなわち「成果をあげることは使命」(『経営者の条件』)との考え方に基づく意思決定のプロセス、及びその実践についてのリーダーにとって不可欠の要求にあります。具体的には、次の決定的なリーダー及び組織の条件です(リーダーとは組織の中で成果をあげることが前提です。ゆえにリーダー個人の資質、考え方と組織の成立条件、つまり「個人」と「組織」双方の条件を同時に扱っています)。
(1)リーダーの仕事は成果をあげることである
(2)成果をあげる能力は習得できる
(3)企業の目的は「顧客の創造」である
(4)マーケティングとイノベーションだけが成果をもたらす
(5)組織は特有の使命を果たすこと、その貢献に集中することのためにマネジメントを行う
(6)そのために、人を活かすこと
(7)社会への貢献
更に、以上の7つの条件には次のような根本的な考え方があります(主にドラッカーに拠るが個人的な思想も挟んでいます)。
(1)リーダーとは成果をあげることに対して報酬を受ける。彼らは自らの組織に対し成果をあげる責任をもつ。成果をあげることになぜは必要ない。リーダーとして当然※とするからである。
(2)成果をあげることは学ぶことはできるが、教わることはできない。つまるところ成果をあげることは教科ではなく“修練”である。
※ドラッカーは次のように言っています。
「すなわち成果をあげることは個人の自己開発のために、組織の発展のために、そして現代の維持発展のために死活的に重要な意味をもつということである。」成果をあげることは松下幸之助さんがしばしば仰っておられた「生成発展」に寄与すること、という解釈ができる。ゆえにこの世に生きているうえでの原理原則に従うことに似ています。
(3)成果とは“企業の外”にうむものである。企業の外に“より良い変化”をもたらすことが成果である。
(4)お客さまのいない会社は存在しえない。働く仲間の幸せさえ担保できない。この当たり前の原則に従えば私たちが集中すべき事は、お客さまの求める欲求を理解・把握し、それに応えるべく商品・サービスをより良くして提供すること。或いはお客さまの真に求めることを知ったならば、いまだお客さまが気付いていない(お客さまの認識の中に存在していない)価値の新たな提供方法を新たに開発すること。そのために既存技術、サービスの提供方法のみならず、新たなモノの見方・考え方を開発して無かった価値を提供することにある。
(5)会社は本業を通じて社会に貢献する。組織は何でもできるわけではない。その強みや存在意義に照らして(理念やパーパス、ミッション)、有限の資源を最大に活かし、集中しなければならない。
(6)組織の最大にしてもっとも生産的にする資産は人間の力であり、人間こそが成果を生む根源である。そのためには「誰もが良い資質」をもっていることを前提にして働く人々への敬意を当然のように重んじることが人を活かすことに繋がる。「マネジメントとは人に関わることである」とはこのような考え方に基づく。ある心理学者いわく「なぜ石鹸を売るように人類に人間愛を売れないのか」との問いに応えることでもある。
(7)あらゆる組織が「社会の公器」である。二度と人類が過ちを犯さないためにも、社会をより良い場所にするために組織は存在する。その最たる存在が会社である。会社は国家・人類社会に貢献し、世界の平和に寄与することを求め続けなければならない。世界の平和とは戦争の回避、その原因になる人間への無理解、無慈悲、貧困の撲滅にある。利益に対する考え方、成果に対する考え方の根本をなすものである。
以上、リーダーのあるべき姿、その資質と持つべき志向及び思考の根本ついて述べてきました。やはり「思考の三原則」がそのまま当てはまるようになお強く思うのです。
■リーダーに至る道、その実践
では実際にリーダーの育成およびその成長の促進はどのようにして行われるべきなのか。そのことについて私見を述べて参ります。一言で言えば、根本的なこと、正しい考え方、原理原則が示されてある書を読み、それを実践する。この繰り返しです。読書の積み重ねは不可欠です。この積み重ねが“量が質に転嫁”するまで行うことです。しかしそのことを自ら発奮してできる人が少ないがゆえに「教育」や「塾」の場が求められています。そうした背景の中で私もお仕事を頂戴しています。
これまでも述べてきたように、碩学の教え、先哲の教訓と現実を併せてみたときに、私は以下の物差しでリーダーになる人を見つめています。読書によって何を実践するのかを掴み実践する、その過程をご支援するのですが、その際にフィードバック、問答、そして教育する際に常にその軸となる物差しです。即ち以下の通りです。
【修身の部】
・「本学」(人間学)の修養を怠らない。つまり人格を高めることを最優先にしているか。
⇒大戦略のトップは哲学(価値観・考え方)であり、戦術、計画という最終局面までそれを徹底するから、結果として”正しく”人が動く
・その「本学」の修養として我が国では先に述べた「五常」、武士道精神(義・勇・仁・礼・誠・名誉・忠義)という土台があった(戦前~90年初頭のリーダー)。これらの徳目は世界的にも評価され続けている古今東西に通貫する資質。この資質をすでに持っているか。
・自因自果、因縁因果の原理原則を涵養し、反省しながら常に実践する
・個人として素直で謙虚(理念のために利己・我利を抑えられる強さ=仁と義)、そして志(野心が公のために向いた自己を突き動かす熱源)
・事業やビジョンを語るとき、常に私は、ではなく“私たち”と言う
⇒コミュニケーション、衆知を集める時間を定期的に設け、組織的な習慣にしている
・「頑張ります」とは言わない=成果をあげるまで諦めない。この事が諦念、諦観に至ることを掴んでいる
・以上のことを通じて、「悲智円満」に至る道を歩んでいる
・そして、常に”上機嫌”、「真摯さの欠如」に陥らない
【マネジメント実践の部】
・原理原則※を見失わない(それほど学び、実践して、原理原則を感知、会得している)
※特にお客さま第一、人財の育成の当事者としての率先垂範
・”AND”の精神を兼ね備えている(人間や物事を一面的に見ない)
・結果よりも成果へのプロセスを持っている(事業の勝ち筋、ビジョンを描き伝える力)
【成果をあげるリーダーのシンプルな尺度】
・三流は短期的、且つ自分の利益を考える(金は残すかもしれない)
・二流は中期的、且つ組織の利益を考える(仕事は残すかもしれない)
・一流は長期的(次世代の先まで)、且つ、社会の利益を考える(人を残す)
⇒ビジョンの本来のあり方
以上が常に観ている物差しです。偉そうに記してしまいましたが、無論自戒も常に忘れてはなりません。常に教育者、指導者はあらゆる人間の鏡であることは大前提です。これは唐の李世民の治世を著した『貞観政要』(マネジメント・リーダーシップの古典)にある3つの鏡(自分を自己観照する鏡・歴史の鏡・出会う人に頂く諫言)を常に忘れないことで律しています。
一流を目指す上で重要なことは、正しい努力の積み重ねです。「広く世の中を諦観する」「経営・マネジメントの原理原則を学ぶ」「正しい考え方を修養する」という素直な学習の蓄積が要求されます。
つまり、日頃から自らを発奮させて正しい努力の積み重ねを怠らないということになります。自学自習がリーダーの実践の前提です。相当に自律した人物であることが求められると思われることですが、いま、この自律性(自らを律し、自らを世の為人の為に活かすための学びと実践に生きること)のレベルは、本来おのずから身につけている筈の40代、50代に至っても相当に低いものと言わざるを得ません。
先ず、自ら書に親しまない。私の知る限り、中小企業のミドルクラス(課長・部長層)の8割は一年間でビジネス書はおろか、古典に親しむことを知りません。人間としての成長に必要な養分を吸収しないまま権限をもって部下の人生を左右する存在になっている状態です。
目の前の仕事だけが全てとの現実に違和感すら抱かない中高年があまりにも多いという現実を、嫌というほど目の当たりにしてきました。因みによく引き合いに出される2020年の米ギャラップ社の調べでは、日本の社会人のうち、仕事に熱心に取り組んでいる人物は全体の5%しかいないとの結果が示されました。残りは「やる気が無い」或いは「周囲に不平不満をまき散らしている」人物で占められるとのことです。
統計データが全てとは思いませんが、コンサルティング業を各企業の現場の方々と交わりながら実践してきたこの10年間で観てきた実態にこのデータは酷似しています(決して中小企業に限定されません)。この流れを次世代にそのままにしておくことは現役世代として無責任と言われても次世代に顔向けできません。ビジョンを考える際にも、リーダーはこうした「10年後、20年後~100年後、そこに生きる後進が“なんでこんな世にしたんだ!”と怒っているとすればそれは何か」を想像することはリーダー育成、人財の育成のみならずイノベーションの観点でも重要な問いです。
■リーダー育成を実践する際の経営者の考え方
経営者の皆さまに置かれては、自社及び社会の公器として次世代にわたるリーダーの育成、排出は長期的な視点が不可欠です。
数年(3年から5年)はもとより、これまで述べてきたような規律ある企業文化、人が育つ素地が会社の中に醸成されてきていない場合、自ずと人が育つ会社になるためには10年はかかるという覚悟が必要です。そして最も大切なことは、内製化するということです。
コンサルタントや外部の人財育成機関に最初は頼ったとしても、10年のうち後半の5年間は自社の中でリーダーを生み出せる組織にならなければなりません。
第三者の風を入れることは大切ですが、人財の育成はお客さま第一の実践と同様、人に関わることゆえに理念に基づいて自らが行えなければなりません。そのために、先ずトップリーダーこそが自ら学び続けていることが切磋琢磨、発展し続ける会社になるための根本姿勢にして必須条件です。
会社なら社長が、部なら部長が、課なら課長が誰よりも“世の為人の為に”学び続けている、そして成長し続けている。この事が決定的に重要です。人を残す経営、そうした長期的且つ全体的、そして根本的な考え方に基づいて、世の為人の為に本業を通じて社会に貢献する会社づくりを目指して頂ければ同志として望外の喜びです。
熊田 潤一