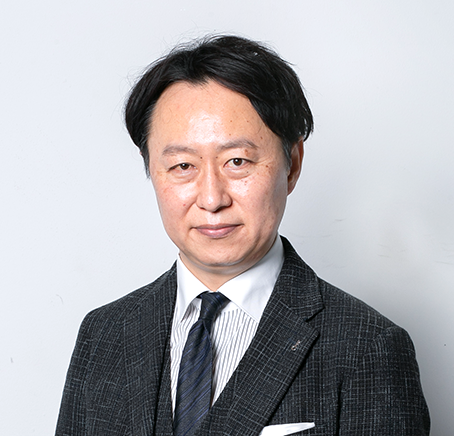(弊社所属のコンサルタントによる長編コラム「KC文集2024」掲載記事)
■日本経済の“失われた30年”の本質は何か
かつて「一億総中流社会」と言われた日本は、この30年等しく経済的にも精神的にも貧しくなっています。例えば日本の所得の6~7割を占める中間層の所得中央値は、1994年に505万円だったのがコロナ禍前の2019年には374万円、つまりこの25年間に約130万円も減っています。
一方、精神的と申し上げたのは、例えば「高校生の心と体の健康に関する意識調査報告書 2018年3月」(国立青少年教育振興機構)によると他国に比べて極めて低いことは報道などでも有名な現実です。あるいは企業に勤める社会人はどうかというと、米ギャラップ社の2021年調査によれば熱意をもって仕事をしている日本の社員は全体の5%(20人に1人)です(米国では35%)。統計だけを観れば経済的にも精神的にも貧しくなってきている、という傾向にあるのは間違いありません。
しかしながら、世界全体でみればまだまだ安全で豊かな国です。とはいえ、この豊かさが表面的なものであることに気付いている人は多いのではないでしょうか。
マネジメントの父にして社会生態学者であるピーター・ドラッカーは、その晩年の2002年に著した『ネクスト・ソサエティ』日本語版の序文で次のように指摘しています。
「日本では誰もが経済の話をする。だが日本にとって最大の問題は社会のほうである。」と。さらには日本の産業構造が製造業からサービス産業への転換が遅れている事実を指摘しつつ「社会心理的にも、日本は製造業の地位の変化を受け入れる心構えができていない。日本は20世紀の後半、製造業の力によって経済大国の地位を獲得した。もちろん日本を軽く見ることはできない。日本はその歴史において、新たな現実に直面し、文字どおり一夜にして転換を成し遂げた実績をもつ。だが、経済発展の主役としての製造業の地位の変化が、日本のかつての難局のいずれにも劣ることのない大問題であることに違いはない。」と語ります。
要すれば、低迷する日本の方向性として、製造業中心の考え方から、新たな価値の源泉への大きな構造的且つ心理的な変化を求めています。
つまりミクロ経済の主体である経営に対しては企業の変革(成り行きではない新たな成長曲線を描くための活動)を前提にしています。その変革の原則は「組織が生き残りかつ成功するためには、自らがチェンジ・エージェント、すなわち変革機関とならなければならない。変化をマネジメントする最善の方法は、自ら変化をつくりだすことである。」と。
私が本書に触れたのは前職(2014年~2016年)の三年間で新規事業のリーダーを務めさせて頂いたときでした。
老舗企業の中で新たなビジネス、新たな組織能力(文化)を構築して何とか事業の成果をあげ、働く人たちの成長と働きがいを高めようと苦悶しているときでした。一言でいえば、仕事を通じて幸せになってもらいたい、と切に願っていました。
そんな悶々と理想と現実のギャップに苦闘しているとき、「自ら変化をつくりだす」、この言葉が私に勇気と覚悟を与えてくれたことをとてもよく覚えています(実は勇気を与えてくれた言葉、考え方にはもう一つ「良い会社」とは何かの3つも勇気を与えてくれた武器になりました。入社前に弊社の小宮から与えられた考え方です)。
当時、事業を進めることはその意味で戦いでした。何の戦いかというと“正しいことを正しい”と日ごろのコミュニケーションから実践、意思決定に至るまで貫徹する、要すれば“正論を通す”戦い、或いは「良い商品があれば売れる、売れないのは商品が悪いから」というビジネスの本質から遠ざかってしまった心の在り方、そして最も厳しい戦いだったのは、「どうせ何を言っても何をやっても変わらない」という組織と個人を覆う重たく冷めた空気に明かりを灯す戦いでした。前述の製造業中心の考え方の典型はまさに“良い商品・製品があれば売れる”という考え方でした。そこにお客さまの真実、お客さまにとっての価値は不在でした。
「自ら変化をつくりだす」、この精神と行動が2010年代に至って組織から失われていたのは決して一部の組織にだけ当てはまることではないと実感しています。ドラッカー先生が語った日本の「一夜にして転換を成し遂げた実績」のひとつである明治維新と近代化を推し進めたリーダーを多く育成することとなった佐藤一斎先生(1772~1859年、儒学者、陽明学者)が示された次の言葉があります。「一燈を提げて暗夜を行く。暗夜を憂うること勿れ。只だ一燈を頼め。」(「永い人生のうちには、暗い夜道を歩くようなこともある。
しかし、ひとつの提灯を提げていけば、いかに暗くとも心配することはない。その一灯を信じて歩むほかはない。」との意。『言志四録』より)。その一燈となったのがまさに「自ら変化をつくりだす」だったのです。私の狭い経験すると、経営や事業がうまくいかなくなった、つまりバブル崩壊から何が企業経営の中で失われたかと言えば、「自ら変化をつくりだす」力を失ったことだと真剣に捉えています。無論、失われた30年を一言で語ることはできません。
日銀も含めた統合政府によるマクロ経済政策の問題もあったでしょうし、長期的に捉えれば戦後GHQの日本および日本人を精神的に骨抜きにして弱体化させる教育政策の成果とも言えます。ただし仕事を通じて世の中をより良くしていくことに責任ある人間としての課題として、「自ら変化をつくりだす」力を復興させることが重要な責務であると捉えるのです。決して推論ではなく、実践を通じて知覚から入ってくる私の直感ともいえる課題感でもあります。
■ドラッカー先生の示唆と安岡正篤先生の「思考の三原則」
時代の不透明感を前に、「今だけ、金だけ、自分だけ」という人間として誰もが持つ魂の弱さに逃げ込む人たちがいます。様々なビジネスの現場にいる人々と接しているとむしろ無意識にそうなってしまっている感覚があります。先に書いたように教育の長期的な残滓とも言えますが、すでに戦後79年が経ちます。そろそろ私たちは未来の世代のために自ら覚醒しなければなりません。VUCA(Volatility=変動性、Uncertainty=不確実性、Complexity=複雑性、Ambiguity=曖昧性)と言われて久しいですが、そんな時代を予見したドラッカー先生は1999年に次のように語ってくれています。
「不透明な時代にあって先見の明のあった指導者は歴史の中にいなかったわけではない。釈迦、キリスト、マホメットを挙げることが出来るが、もっと身近な人物を求めるなら、明治の指導者たちに学ぶべきだろう。」(出典:P.F.ドラッカー 『日経ビジネス 1999年4月5日号』)
日本通であり、親日家でもあったドラッカー先生なりのエールとも受け取れますが、同じことは幕末、明治期に来日して日本人及びそのリーダーたちを直接知覚した当時の外国人たちも同じことを語っています。では、明治の指導者(リーダー)に学ぶべきだとするならば、その本質はどこにあるのかというと、それは昭和の漢学者、陽明学者である安岡正篤先生の次の言葉がそのヒントになるのではないかと思うのです。
「今日の日本の堕落、頽廃、意気地のなさ、こういう有様は昨日今日のことではない。非常に長い由来・因縁があるということを考えないと、これを直すことはできません。皆さんが今後起こってくる諸般の問題をお考えになるには、目先の問題をとらえた流行の皮相な理論では駄目でありまして、先程申したように、少なくも明治以来の思考の三原則によって徹底した考察をなさらないと正解を得られない。したがって、今後の真剣な対策も立たないということを私は信ずるのであります。」(出典:安岡正篤『運命を創る』、※下線筆者)
今後起こるさまざまな現象に対して、本質的な対策を講じるにはこの「思考の三原則」によって徹底した考察をしないといけない、と語っています。ここでも“明治以来”と安岡先生は語ります。ではその「思考の三原則」とは何か、それは次の3つになります。
・長期的に考える
・多面的に全体を考える
・根本的に考える
まさに「今だけ・金だけ・自分だけ」の真逆の視点で考えよ、と言っているのです。過去の日本的経営の成功要因を私たちは昭和の高度経済成長からバブル時代に至る“三種の神器”(終身雇用・年功序列・企業内組合)としてきました。そのことは体力がものをいう製造業的なモノ中心の考え方の上で確実に当時は機能していました。
1970年には未来学者のハーマン・カーン(1922~83年)が『超大国日本の挑戦』において「21世紀は日本の世紀」と断言し、また社会学者のエズラ・ヴォーゲル(1930年~)は1979年『ジャパン・アズ・ナンバーワン』の中で日本の高度経済成長の成功要因を分析し、声高に“日本的経営”を称賛しました。いまでは、そんな時代もあったのか、と若者は思うでしょう。
しかし、約30年間も伸び悩む日本経済の中で、昭和のやり方ではもはや古い、平成のやり方では何も浮上させ得なかったことを私たちは反省しなければなりません。
三種の神器にも良いところはあったと思いますが、いつの時代にも発展をもたらすもっと根本的な神器が必要だと考えます。
例話の世にこそ、それを取り戻し、当たり前のことを当たり前に徹底できる世にしなければならないと考えます。もっと根本に戻る、そうした時のヒントがドラッカー先生や安岡正篤先生の前述の示唆、そしてそうした時代の根本的な実践的精神を宿した松下幸之助さんをはじめとする明治の指導者を直接知る経営者たちの大切にしてきた思考と実践に求められるのではないかと考えます。
失われた30年、私は何が失われたかを考えるときに、同じ人間、同じ日本人の歴史をもう少し長い目で見渡すと、この150年~300年ほどの歴史で見た方がより本質と向こう100年のとるべき方向性がみえてくるのではないかと直感しました。その直感は、何が失われたのか、それは現象だけ見れば経済的な発展ですが、その根本にあるのは精神の問題だと考えるに至ったのです。
この10年間だけでも、中小企業から大企業まで自身も働き、リーダーを務め、さらにはコンサルティングの仕事として1000人以上のリーダー(経営者、役員、部長・課長といった中間管理職等)と向き合ってきました。そこから得た直観です。
そこで、次世代をより豊かにするために、経営(マネジメント)として大切な考え方を「思考の三原則」に立ち返って、常に申し上げてきたこと、つまり確信について述べます。以前(具体的には明治~昭和一桁)にはあったけど“この間に失われたこと”を再確認するということです。
■長期的に考える
経営(マネジメント)で大切なことは方向づけです。シンプルに言えば、私たちの会社(事業)は、どこからやってきて、どこに向かおうとしているのか。そこから現在地を認識することです。過去現在未来という、時の原則に従って長期的に考える思考法です。どこからやってきたかは、つまり会社や事業の歴史、創業の精神、そして何を大切にしてきたかの目的と価値観です。船でいえば錨のようであり、空を見上げれば北極星のようなものです。
目的とは過去から未来に至るまでを貫くものです。そして自分一代では成し遂げられない、永遠に追い求めるものです。仕事とは“人に仕えるのではなく、事に使えること”と日頃若い方々には語りかけてきました。その「事」こそが目的です。
何のためにこの会社が存在しているのかという存在意義と、未来永劫何を大切にして仕事を、事業を営んでいくのかということです。表現上の誤解を恐れず申し上げれば、この“何のために”がなければ、人間は精神的に奴隷のように働いてしまいます。
言い換えればやらされ感のようなものです。やがて何も考えずに作業を繰り返す、やがて言われたことすら満足にできない人間となってしまいます。
できなくなった自分を省みて未来に絶望するのかもしれません。長い歴史の中で人類は自由を得ようとして汗を流し、涙を流し、時に血も流しました。自由の反対は奴隷です。物心両面で一方的に奪われるだけです。
人間はそんなに弱くない、と思いたいところですが、歴史的に見てもその姿は厳しいものです。私の持論ですが、現代において人間が肉体的に奴隷となるのは、精神的に奴隷となった後です。実際に、これまで1000人以上の働く人々と1対1の対話、ヒアリングを重ねてきましたが、「生活(お金)のために“だけ”働いている」という人のほうが圧倒的に多いのです。
またその実態の中に、誤ったマネジメントの理解による弊害も多々出くわします。それはリーダーシップとマネジメントに対する誤解です。外からの力による影響を与えて人や組織を動かそうとする人間が後を絶ちませんが、それは心理学では外発的動機と言われます。
無論、一人の人間の心を動かせない人間が組織を動かすことは不可能なはずです。マネジメントにおいてこの外発的動機によるリーダーシップの発揮を交換型リーダーシップ(飴と鞭を交換する、との意味)と言いますが、この外からの影響力を発揮すれば、短期的には人は動きます。短期的な業績も得られることもあります。
しかし、やはりどこまでいっても短期的です。もって3年、短ければ3か月で組織を崩壊せしめます。これは私のマネジメント経験による実感です。人間の精神を衰退させ、組織の精神を破壊してしまいます。
一方、内なる動機、内発的動機と言いますが、これであれば個人も組織も持続的に発展が可能になります。この一燈に頼むことがマネジメントでは決定的に重要です。
働く仲間を奴隷にしないために、内なる動機による仕事、事業、そして組織を目指す流れをもう一度徹底的に布教しなければならないと危機感を覚えています。布教といったのは、コンサルタントのある意味限界を自覚しなければならないということです。
組織を方向付けし、直接動かすのは、そこにいるリーダーだからです。意味と意識の両方で刺激物になる、それが宣教師としての役割だからです。物事を長期的に考えるためには、過去現在未来という一線を貫く目的と価値観が必要です。ひとそれぞれ人生観は違っても、仕事観・経営(マネジメント)観は一貫して共有できるのです。
この一燈を頼むこと、それが何世代にもわたって長期的に考える根本だと信じます。
一方、歴史から学ぶことで物事を長い目で見ることもできます。どこまで行っても経営もビジネスも、人間が為すことです。組織も一人ひとりの人間の集まりです。
例えばペティ・クラークの法則というものがあります。成熟した社会・国家では産業は一次産業から二次産業、やがてその二つを抱き合わせながらサービス産業が社会のおもな産業に発展していく法則です。これを知れば、“良いモノだけを作っていれば売れる”はただの幻想です。
確かに、良いモノにこだわり続けることは大切なことです。
しかし現実、それだけではコモディティ化に巻き込まれ、価格競争になっていきます。この世には出して良い商品(経済用語で「財」)・サービスと出してはいけない商品・サービスがあるだけですが、大切なことはモノに付加価値、つまり顧客にとってプラスアルファの価値を創造し続けることができるかどうかです。
「諸行無常」という世界観も重要になってきます。或いは、長期的に考える際に重要な法則にヘーゲルの弁証法があります。アウフヘーベン(正反合を繰り返し世の中は発展していく)や古くなったものが新しい価値を伴って復活してくる螺旋階段的な発展の法則や、量は質に転嫁するといった法則です。
こうした原理原則、歴史が明らかにした世の法則を知っていると、未来を予見する武器になります。その意味で、「マネジメントとは教養である」とドラッカー先生は語っているのです。こうした“知の統合”こそマネジメントを実践するもののすでに持っていなければならない知性なのです。
この教養は戦前の教育では実に青年になるまでの間に色濃く存在していました。戦後教育でその根本は完全に蔑ろにされたこと、その結果が先進国一学ばなくなった日本人の現在とみて差し支えないと思います。
■多面的に全体を考える
世の中も、組織も、一人ひとりの人間事情も、ただ一言、複雑です。その複雑さを排除するのではなく、複雑なまま見ること。これを仏教用語では「正見」(ありのままの真実を正しく見る)と言います。この十数年、ダイバーシティに始まり、インクルージョン等の人間と文化の多様性を受け入れる運動が喧しく経営の世界でも語られます。
確かに大切なことですが、いうなれば、当たり前のことです。戦前、さらには江戸時代、識字率が圧倒的に世界一だった国は実は日本でした。海外列強(戦前、近代の大国はイギリス、ロシア、フランスそしてアメリカ(アメリカはペルー来航時、まだ大国ではありません)、さらにその前であればオスマントルコ、オーストリアハンガリー帝国等)は階級によって教育に大きな差があったことは有名ですが、我が国にはそれはありませんでした。最近はリベラルアーツ(一般教養)と言われますが、このリベラルーアーツこそ字の通り、自由になるための知の技能だったわけです。
例えば渋沢栄一は農民(商品作物の生産販売も兼ねた豪農ではあった)出身です。世界恐慌から日本をいち早く脱出させた高橋是清に至ってはアメリカで奴隷を経験しています。戦前、日本の近世近代は武士の時代が長く、明治維新後も男性中心と言われますが、表に出ていないだけで、日本の女性にもたくさんのリーダーがいました。
日本の家制度を守ってきたのは上州で有名な“かかあ天下”に象徴されるように力強い女性たちでした。しかしこうした歴史も現代ではどうも偏った見方、西洋的な歴史観を押し付けられてどうもうまくいっていない(日本の実情、文化)と感じます。松下幸之助さんはこう語ります。
「(日本の山野に)いろいろの花があってよかった。さまざまな木があってよかった。たくさんの鳥があってよかった。自然の理のありがたさである。人もまたさまざま。さまざまな人があればこそ、ゆたかな働きも生み出されてくる。自分と他人とは、顔もちがえば気性もちがう。好みもちがう。それでよいのである。ちがうことをなげくよりも、そのちがうことのなかに無限の妙味を感じたい。無限のゆたかさを感じたい。そして、人それぞれに力をつくし、人それぞれに助け合いたい。いろいろの人があってよかった。さまざまな人があってよかった」(出典:松下幸之助『道をひらく』「さまざま」より)と。
少し長い引用になりましたが、この松下幸之助さんの言葉の中にも、マネジメントの原理原則が詰まっています。
このことは人と組織の全体を考える際には不可欠な視点ですが、この実践には「人間学」の修養が不可欠です。この「さまざま」を統合して組織の外に成果をあげるために方向づけるのがマネジメントです。
この「人間学」を古くは「本学」と言いました。本末転倒の語源にもなっていますが、出典は戦前の教育でも用いられた『大学』です。かつて日本の小学校に必ずあった二宮金次郎像、日本でもっとも大切とされた資産である勤勉の象徴ですが、その金次郎少年が両親を失って叔父の家に世話になっているときに薪を背負いながら読んでいたのが『大学』です。『本学』とは人間学のことです。私たちはいかに生きるのか、何のために生きるのか、人間としての正しい道とは何か。『マネジメント』の中でドラッカー先生が語ったマネジャーがすでに持っていなければない資質である「真摯さ」について学ぶことです。
一方、生きるために身につける技術、手段のことを「末学」と言います。いまの学校教育はこの「末学」に偏ってしまい、人間学、特に公共心を育むことが少なくなってしまいました。「世界に一つだけの花」はもともと日本人の文化です。八百万の神というように、私たちは元来、異質なものを排除することはありませんでした。
村八分は江戸時代からの風習でしたが、村の掟(公共の福祉)を破った家がその憂き目にあいます。
しかし火事と葬式だけは例外(それで八分)。歴史的事実を帰納的に見て公共を大切にする心は以前はどこの国よりも深かったと私は感じています。
明治の近代化では福沢諭吉が『痩せ我慢の説』で語ったように、「わたくしこそが公なり」の精神を慶應義塾に遺しました。今では海外の留学生、特に途上国の留学生がその精神を自国に持ち帰って活躍しているそうです。多様で複雑な社会や組織を発展的なものにするためには、まさに「自由の中の規律」、その地域や組織の一定のルールを守ることは当たり前の話です。何でもあり、ではないのです。自由の為には規律が必要です。和して同ぜず。わが国では聖徳太子の時代から「和を以て尊しとなす」ですが、より正確に全体をマネジメントしていくならば、「和するを尊しとなす」でしょうか。
経営の方向づけに多くの影響を与える外部環境も内部環境も複雑です。
複雑さを複雑なままみて構造化する「システム思考」や経営の「エコロジー理論(環境・自然の与える大いなる運命、環境を受け入れて経営する)」や多様な関係性を和して構築していく「ソーシャルネットワーク理論」など、横文字のさまざまな理論も経営学で提唱されますが、何れも原理原則、人間として正しい考え方を実践をもって会得した先人に学ぶことで、その本質が見えてきます。複雑さ、多様さもまた一つの原則に収斂されていくべきものです。
ドラッカー先生曰く、経営(マネジメント)の原理原則を正しい考え方をもって実践し、教育し、成果をあげた最初の人物は日本の渋沢栄一です(『マネジメント』参照)。不透明で複雑な時代というならば、世界史上、経済と社会の大変革を短期(15年~30年)で二度も成し遂げた日本の先人から学ぶのが早道だと、ドラッカー先生は言いたかったのではないでしょうか。
「多面的に全体を考える」、実は後半の「全体を考える」も抜けがちです。多くのビジネスパーソン、特にリーダーにこの全体観が抜け落ちることは、仕事に意味と意義を与えることを怠らせます。先の「長期的に考える」ことにも強く影響します。
私はよく「仕事の全体像」「マネジメントの全体像」「事業の全体像」をかならず働く仲間と共有することを常に求めています。この仕事がどこに繋がっているのか、この作業は何のために必要なのか、この事業を成し遂げた先にはどのようなより良い変化があるのか、そしてその全体像の中で現在「いまここ!」に集中すべき意義が見いだせるからです。
これも原理原則、正しい考え方を理解し、自分の体にしみ込ませれば、どこでもある程度は通用する全体像を描くことはそんなに難しいことではなくなります。
中長期のビジョンを描きそこに組織全体のエネルギーを統合させる際にも全体像は必須です。明治のリーダーを多く輩出することになった佐藤一斎先生は次のように語ります。
「物事を処理する場合、まず考えておかなければならないことは、「仕上がり」(完成図)を予測して臨むことである。そうでないと、舵のない船で漕ぎ出したり、的のないところに矢を射るような愚行となる。」(出典:佐藤一斎『言志四録』)
またドラッカー先生も『マネジメント・上』の中で「そもそも仕事とは、全体として把握すべきものである。分析の不可能なものである。だが知覚の力によるならば、容易に把握できるものである」と断言しています。ここでいう知覚とはまさに直接真実に当たる、ということです。
原理原則を学んだのなら、直接その真実と向き合って実践しなければなりません。真実と向き合うこと、そのスタートが直接知覚することです。知覚とはいわば五感で直接感じることです。私は営業が長かったですが、営業でいえば、どれだけお客さま(まだ自社の顧客になっていないノンカスタマー含め)と直接同じ空間で直接向き合ったかが営業の質を左右します。それは頭で考えることではなく、知覚で感じることによる直観です。
知覚をフルに磨くにはオンラインでは難しいものです。なぜならば人と人の関係を作るコミュニケーションでは波動が生じ、その波動のレベルで相手のことを感じ取ることが本質だからです。それを知覚によって、と解釈しています。因みにドラッカー先生は「知覚は論理ではない。体験である。」(『マネジメント・中』)と語ります。そしてこのことは次の「根本的に考える」ことにもつながります。
■根本的に考える
安岡先生が未来を生きる我々に訴えた明治以来の思考の三原則、その最後は「根本的に考える」です。ある意味、三原則のうち「長期的」「多面的に全体」を統合する、あるいはその2つの土台になるのがこの「根本的に考える」力だと個人的には捉えています。
根本的にまず何を考えるか。本稿を読み進めた方であればすでにそれは見えているかもしれません。それは要するに「世の中の発展法則(生成発展)」、「原理原則」、そして「人間としての正しい考え方」です。特にビジネスでも人生でも、すべて人間に関わることです。それと同時に人智を超えた運命に関わることです。
そしてその多くは歴史の中にしか教材はありません。歴史を学ぶことこそ生きる力を養う学問でした。世の中を発展させた偉人から学ぶことも含みます。「正しい考え方」を深める学問として「人間学」があります。昔は学問と言えば国語算数理科社会ではなくこの「人間学」でした。これも人類の、国の、世界の歴史を知らずして深く理解することはできません。それらの重要な教養を国の教育から意図的に奪われたのが戦後生まれの我々です。そこに気付いて、学びなおさなければなりません。リスキリングももちろん重要ですが、それは「末学」です。「本学」こそ学びなおされるべきだと強く思います。
殊にリーダー、或いはリーダーを志す吾人。リーダーに人間学が不可欠なのは先にも申し上げてきましたが、私たちが根本的に、要すれば様々な現象から本質を見出す力を得るためには“本末転倒”は許されません。
そのためには思考の三原則を駆使していた先人たちが学んでいた共通の教養にして知行合一の対象であった古典(四書五経、特に『論語』『孟子』『大学』『中庸』の四書)に学ぶこと。或いはドラッカー先生が教えるように幕末の指導者、明治の指導者のうち、世を変え、人を残した偉人の殆ど(例えば佐藤一斎先生、その弟子佐久間象山、山田方谷、横井小楠、さらにその弟子、孫弟子筋である吉田松陰、高杉晋作、一斎先生の教えを抄録して大切にした西郷隆盛、そして『論語と算盤』に代表される道徳経済合一説で現代にいたる豊かさを遺した渋沢栄一、等々)が学んでいた強烈な実践主義(到良知、知行合一)である「陽明学」を学ぶことが大切です。
明治の2大ベストセラーの一つ『西国立志編』(スマイルズの『自助論』をこれも佐藤一斎先生の直弟子である中村正直が翻訳)や『学問ノススメ』など、私たちが学ぶことができる古典や実践本は有り難いことに簡単に手に入るものばかりです。安岡先生は次のように私たちに一燈の勇気を与えます。
「新しい時代を創造するような人物は、知識の学問や技術の学問からは生まれない。やはり智慧の学問、徳の学問、そういう教育の中から出てくるのである。」
(典拠:安岡正篤『[新装版]知命と立命 人間学講話』)
また仕事や経営の「原理原則」を常に外さないことも根本的に考えることです。再びドラッカー先生の言葉を借りれば、次の至言が真っ先に思い当たります。
「転換期にあって重要なことは、変わらざるもの、すなわち基本と原則を確認することである」
「いかに余儀なく見えようとも、またいかに風潮になっていようとも、基本と原則に反するものは、例外なく時を経ず破綻する」
(出典:P.F.ドラッカー『マネジメント〔エッセンシャル版〕ー基本と原則』)
この基本と原則の中で最も重要なことは、「お客さま第一」の精神と実践です。その営みの始まりは常に次のことを確認しなければなりません。
「マーケティングとは、企業の成果すなわち顧客の観点から見た企業そのものである。したがって、マーケティングに対する関心と責任は、企業のあらゆる分野に浸透させなければならない。」
(出典:P.F.ドラッカー『マネジメント・上』)
つまり、マーケティング(=お客さま第一の実践)は全社員の仕事であると言っているのです。
さらにそのプロセス、手段は次の至言をもって、現在も最先端のマーケッターが共通の原則としているものと符合します。
「顧客の心を読もうとするのでなく、顧客自身から直接答えを得るべく意識して努力しなければならない。」
(出典:P.F.ドラッカー 『マネジメント-課題・責任・実践』)
特に重要な顧客、つまりお客様に喜んでいただく商品・サービスだけが会社の存続も働く仲間の働く喜び、働きがい、その先にある生きる喜びと経済的な豊かさもあるのです。因みにそのお客さまは一人ひとりの人間です。経営の原理原則はドラッカー先生に学ぶのが基本ですが、その原著には次のようにあります。
「Because its purpose is to create a customer, the business enterprise has two—and only these two—basic functions: marketing and innovation. Marketing and innovation produce results; all the rest are “costs.”」※下線筆者
(出典:Peter F.Drucker『Management: TASKS,RESPONSIBILITIES,PRACTICES』
「企業の共通の目的は“顧客の創造”である」で有名な一説ですが、その際の顧客とは、“create a customer”つまり“一人の顧客”への理解から始まるということです。会社が大きくなると、否、中小企業様であっても、仕事に対する謙虚さ、素直さ、感謝の念を忘れた会社組織とその従業員となると、この“一人のお客さま”の視点を見失っています。やがて成果もあげていないのに給料をもらって当たり前、となるのです。企業は、会社は個人の生活を支えるものですが、決して社会保障機関ではないのです。お客さま、一人ひとりに喜ばれて、その積み重ねが現在の会社の姿であることは、新入社員から経営者に至るまで、片時も忘れてはなりません。このことを忘れた会社から時を経ず破綻するとドラッカー先生は警告しているのです。
■さいごに
思考の三原則の一つ「根本的に考える」、その際の人間としての正しい考え方、仕事の原理原則を知り実践すること、このエッセンスは多くの会社が理念や信条、或いは行動規範(ウェイ、バリュー)にしていることではないでしょうか。以前1000社ほどの理念を研究したことがありますが、大半は上記の原理原則、正しい考え方を大切に明記しているものです。しかしその実践の徹底の差が成果と結果の違いを生んでいるとはっきり言えます。コンサルティングをさせて頂いているとある建設業や製造業の会社様では従業員の定着率が5年で50%という低さでしたが、その会社様にも立派な遺訓、先人が残した素晴らしい理念があるのです。
その理解のための教育と実践の徹底を繰り返す中で、今では離職率は一桁台にまで下がっています。働く仲間の採用にしても、お客さまにご満足いただく実践も、働く仲間の幸せを実現するにも「はじめにないものは、最後までない」のです。この一貫性が決定的にマネジメントの成否を決します。
私はいつもリーダーの皆さんにその徹底を求めています。リーダーがまずビジョンを描くとき、仕事を始めるとき、目標を乗り越えようとするとき、根本に立ち返るのはどの企業、どの組織のリーダーであっても自社の理念、目的の筈です。その徹底、それが差を分けるのです。
会社の理念や目的を深く理解するためにはこうした原理原則、正しい考え方に裏打ちされた基本的な教養が必要です。思考の質に関わることでもあります。思考(考える力)の質を高めるためには、習慣によってインプットとアウトプット(実践と成果)の量を増やすことです。量は質に転嫁します。
それを信じて、一歩ずつでもやれるところから、読書・勉強と実践を増やしていくこと。その努力の積み重ねが、私たち、そして次世代。その先の子々孫々へ明るい道をひらいていくことを深く信じます。
同じ志を持った多くのリーダーと切磋琢磨する日々を楽しみつつ、逆境も順境も思考の三原則で共に学び、共に乗り越え発展し続けること、命尽きるまで実践し続けたいと思います。
熊田 潤一