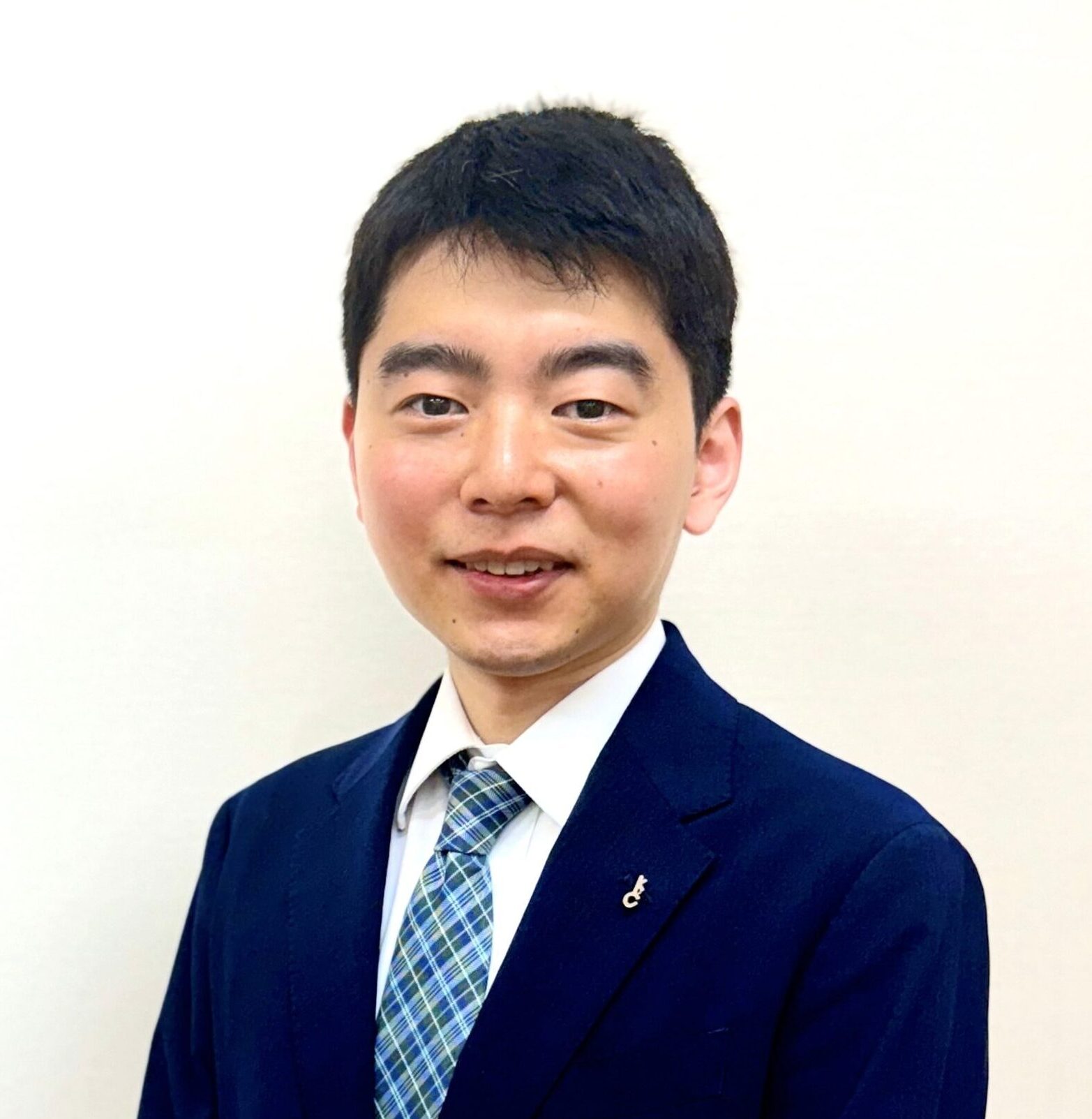8月下旬に、イギリスの空母「プリンス・オブ・ウェールズ」が東京港に入港したというので、興味を持ち現地まで見に行きました。空母(航空母艦)とは、多数の航空機を搭載する海上の航空基地のような船のことです。近くの公園から外観を見ただけでしたが、全長284m、満載排水量6万t超の同艦を目の前にすると、その大きさや、甲板に並んだ艦載機の迫力に圧倒されました。
歴史に詳しい方は、第二次世界大戦時に存在した、英国の同名の戦艦を思い起こされたかもしれません。1941年の真珠湾攻撃に前後して行われたマレー沖海戦にて、日本軍の攻撃により沈没したのが戦艦プリンス・オブ・ウェールズです。今回の航海の帰途には、日英両国による追悼式典も行われるとのことです。
空母プリンス・オブ・ウェールズの来日の目的は、もちろん追悼のためだけではありません。アジア太平洋地域への英国の関与を示すとともに、周辺国への圧力を強めロシアへの支援を継続する中国を牽制し、その動向を探ることも目的と考えられています。
4月に英国を出発した同空母は、地中海やインド洋、シンガポール、豪州などを経て4か月をかけて日本まで到達しました。その間自国周辺を留守にしていますので、イギリスのアジア太平洋地域へのコミットの強さが窺えます。同時にそれほどまでに、アジア太平洋地域の安全保障リスクが高まっている、ということの現れともとらえられます。米国が単独行動主義に戻りつつある今、日本は同地域の安全保障について現実を直視し、いよいよ主体的に行動する必要がある、ということではないでしょうか。
加えて、有事を想定するにあたっては、「今の」脅威をしっかりと理解し対処することが必要と考えます。終戦より80年の今年、戦争の記憶を風化させないためにどうするか、といった報道を多く目にします。過去の体験を語り継ぐことはもちろん大切だと思います。一方で、我々が想像する有事は、太平洋戦争のイメージにあまりにも縛られているのではないか、とも思えることがあります。
有事になった際の戦い方は、太平洋戦争のそれとはまったく別物になるはずです。例えば、空から焼夷弾が落ちてくる代わりに、(想像ではありますが)まずサイバー攻撃により電力やガス、通信、金融等インフラが一斉に停止し都市機能が麻痺、その混乱に乗じ敵軍が侵攻するといった具合です。過去の経験だけにとらわれず、今現実に起こりうる脅威についても直視する必要があるのではないでしょうか。
冒頭で紹介した戦艦プリンス・オブ・ウェールズは、1941年1月に就役したばかりの最新鋭艦でした。しかし、当時ほぼ想定されていなかった航空機による航行中の軍艦への攻撃により、就役からわずか1年足らずで沈没し、英国のチャーチル首相は大きな衝撃を受けたといいます。軍艦同士の砲撃で決着をつける、というそれまでの常識が覆り、航空機主体へとまさに「戦い方」が大きく転換したのです。
同名の空母が、日本にとり今や「準同盟国」となったイギリスから来日するのは、まさに隔世の感があります。同時にそれは、終戦から冷戦期を経て大きく変化している現在の安全保障の状況や、想定すべき有事のありかたの変化をも示しているようにも思われます。もちろん何も起こらないのが最も喜ばしいですが、有事の際にも対応できる体制を作っておくことが、逆説的ながら抑止力につながるはずです。企業のBCPと同じく、国や国民としても、現実を直視し、それに備えることが重要ではないかと考えます。
小宮 弘成