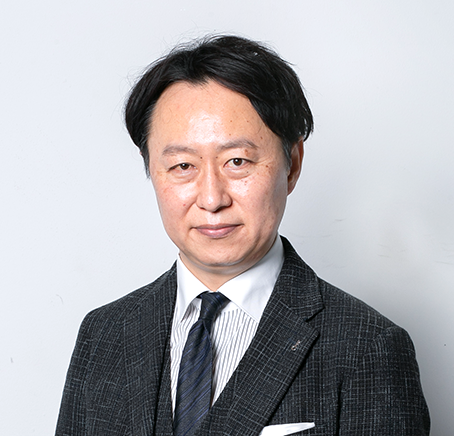◆思考の質が集中すべき行動を変える
現在数社の「変革」を支援しております。変革にしても通常の事業運営にしてもその全体像を描いて共通の目的、目標に社員の全熱量を注ぐ環境をつくることが大切ですが、その全体像の中でも社員に求める行動が何であるのかを明確にできるリーダーは少ないものです。共通の目的・目標、その先にある成果(お客さま、関わる人びとのよりよい変化に対する評価)に向かう全体像のなかで、その変革を牽引するリーダー(最高責任者は経営者の場合もあれば、役職に関係なく有志のリーダーもあり)に不足しがちなのが「行動の変化の前に理解の変化を迫る」ことです。このことは弊社コンサルタントの新刊『集中経営』(新宅剛・藤本正雄著)でも示されていますが、同じく先にドラッカー先生は以下のように指摘しています。
「成果は自動的に生まれるものではない。ハウツーによって簡単にできることではない。試行錯誤で得られるものでもない。組織は、われわれ人間にとっての新しい環境である。したがって、それは新しい資質を求める。同時に、新しい機会を与える。行動の変化よりも、まず理解の変化を迫る。」
(出典:P.F.ドラッカー『イノベーターの条件』)
何をするにも成果・結果を得られるのは正しい考え方による理解を伴った行動があればこそです。ただの行動ではなく時間と熱量の集中を必要とします。時間、人、モノ、そして資金もあらゆるものに限りがあります。何の「理解」の変化かは、方向付け(理念・ビジョン・行動規範=マネジメント・仕事のルール)への理解です。個人個人の価値観は様々であっても、仕事の価値観、ルールは共有しなければなりません。この一貫性を生み出す徹底がリーダーの最重要の仕事です。
◆「理解の変化」のためには「敬意」「未来の成長」と共に「時間」をかける
ここでもドラッカー先生の示唆を先に共有します。
「人のために時間を数分使うことはまったく非生産的である。何かを伝えるにはまとまった時間が必要である。方向づけや計画や仕事の仕方について15分で話せると思っている者は、単にそう思い込んでいるだけである。
肝心なことをわからせ何かを変えたいのであれば1時間はかかる。何らかの人間関係を築くには、はるかに多くの時間を必要とする。知識労働者との関係では特に時間が必要である。上司と部下との間に権力や権威が障壁として存在しないためか、あるいは逆に障害として存在するためか、それとも自意識のためか、理由はともあれ知識労働者は上司や同僚に多くの時間を要求する。」
(出典:P.F.ドラッカー『経営者の条件』)
私がいつも推奨するのはこの「理解の変化」のための時間を最低でも1週間に2時間は使うことです。例えば私が事業変革のリーダーを務めていた時は毎週月曜日の午前中3時間はメンバーに必ず時間を空けてもらうルールを設定し、そこで事業の目的、目標、共通の価値観(行動規範)を徹底して説明、対話し、その上で今週はどのような行動に集中するのか、先週の行動、成果は何か、そしてそこから導き出せる共通の教訓とは何かを共有していました。このくらいしてようやくついてきてくれるメンバーの未来の成長、責任の明確化、成果をあげることで得られる貢献の実感が組織に伴ってきます。
【求める理解の変化:5つのP】
私は以下の4つの理解の変化の徹底を常に要求します。
1.Philosophy:会社の理念、思想、リーダーの「観」=ビジョン
2.Paradigm:モノの見方、考え方(歴史観を伴った状況、外部環境のとらえ方)
3.Principle:原理原則(共通の行動規範、共通のルールの根拠)
4.Policy:方針、方向性(戦略の軸)
5.Plan:具体的な戦術・作戦と計画(PDCAのCの軸、タイミングも明確にする)
上記で最も大切なことは信頼の基である全てに一貫性を持たせることです。そのために最重要なことはリーダーの「観ていること」(人間観、経営観、仕事観など)が何であるか、そしてそれがメンバーの幸せにどうつながるのかを意識することです。人は当初「利」についてくるからです。例えば政治でいえば現在の我が国のトップの「国家観」はどうでしょうか。目先の利益を追っているのか、長期的な国益と国民の幸福のための「観」があるのか。選挙の時だけではなく、多くの国民はその有無を感じ取っているのではないでしょうか。
また、なぜこれだけ「理解の変化」への時間をかけるのか。それはともに働く仲間、ついてきてくれるメンバーへの人間としての敬意があるからです。誰でも正しい理解に基づく行動(お客さま第一とは具体的に何をすることか、何が最もお客さまの価値にとって重要な行動なのか)を通じて成果をあげ、成長することができる。成長の先には各々の掴み取りたい幸福がある。そのためにリーダーは何としても成果をあげ結果を出してもらう覚悟をもたなければならないのです。社員の幸福は正しい成果を伴った結果を出さない限り、絵空事になってしまいます。共に働く組織に働きがい、生きがいを生み出し、仕事が作業にならず常に「事に仕える(=大いなる目的に仕える)」環境をつくり、働く喜びが得られない冷めた組織にしないことが未来をより良くするために仲間の未来の成長に責任を持つことがリーダーの使命であると考えます。
熊田 潤一