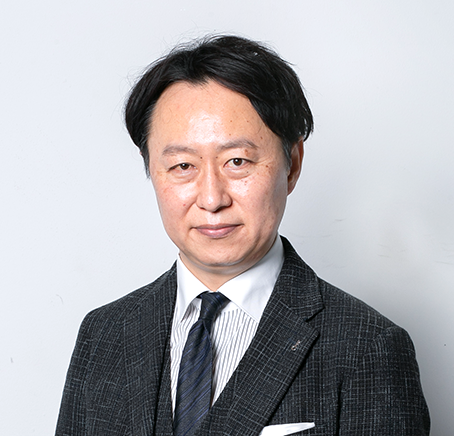(『論語』「里仁第四 二五」(金谷治訳注 岩波文庫版)より)
今週の「言葉」は、孔子とその弟子たちの問答集である『論語』からの一節です。「子の曰わく、徳は孤ならず。必らず鄰あり。」(原文:子曰、德不孤、必有鄰)とは、「道徳のある者は孤立しない。きっと親しいなかまができる。」と孔子は言っているのです。
目下複数のお客さま先で経営幹部育成のお手伝いとともに、いくつかの変革のプロジェクトをご支援しています。
変革とは現実の先にある成り行きの未来が、到底次世代に残せる状態ではないと感じ取った者が自ら起こす取り組みです。これまでと同じやり方で違う未来は期待できません。
「同じことを繰り返しておきながら、異なる結果を期待するとは、きっと頭がどうかしているのでしょう。」アインシュタインが語っていますが、この種の仕事が変革です。
従って現状の近世の高い仕事の上で、将来のために重要なことへの取り組みを自ら主体性を発揮して取り組むことになります。変革をけん引するリーダーは基本的に最初の数か月、場合によっては1年くらいは「孤独」なものです。
組織とは人間の集まりであるがゆえに、ほとんどの人は「変わりたくない」という脳の作用が支配します。
そのなかで「新たにこうしよう、ああいよう」といえば多くの人はついてきません。「現状維持」が「気持ちが悪い」「危険だ」或いは「このままではまずい」という危機意識や切迫感が心理的に働かない限り(脳の感じ方が変わらない限り)、変革を起こそうとするリーダーに聞こえてくるのは陰でも表でも批判や非難の言葉です。そこで半年くらいでその孤独に耐えかねて変革を途中で取り下げてしまう例も少なくありません。
変革は一度始めたら屠龍で頓挫することが許されません。なぜか?それは「どうせまた変わらないんでしょ」という空気を組織に倦んでしまうからです。やるからには高い理想(ありたい姿)の実現に向けて「あきらめない限り失敗はない」という精神で小さくとも成果をあげるまでやり切ることが重要です。
変革を成し遂げたリーダーだけが観ることが出来るあらたな景色があります。しかしその景色を観るまでは常に不安や焦燥感が付きまといます。
この状況をやり抜いていくためには「孤独」な時間に耐えるだけの信念が必要です。その信念として最も説得力のある教えがこの「徳は孤ならず。必らず鄰あり。」です。
リーダーは、或いはリーダーを志すならば、この孤独な時間(一人の時間)を愛し、自らの徳(仁・義を貫く人格)の研磨の習慣お時間にすることをお奨めします。徳は一生磨き続けるものですが、先義後利、自因自果、自利利他の姿勢を徹底することで、少しずつ仲間が増えてきます。そのことを信じて進んでいきましょう。最後に明治のリーダーの多くが学んだ佐藤一斎先生の言葉をお贈りします。
「一燈を提げて暗夜を行く。暗夜を憂うること勿れ。只だ一燈を頼め。」
(人生のうちには、暗い夜道を歩くようなこともある。しかし、ひとつの提灯を提げていけば、いかに暗くとも心配することはない。その一灯を信じて歩むほかはない。)
熊田 潤一