一部門だけの現場経験で社長に。そこで感じてきた壁。
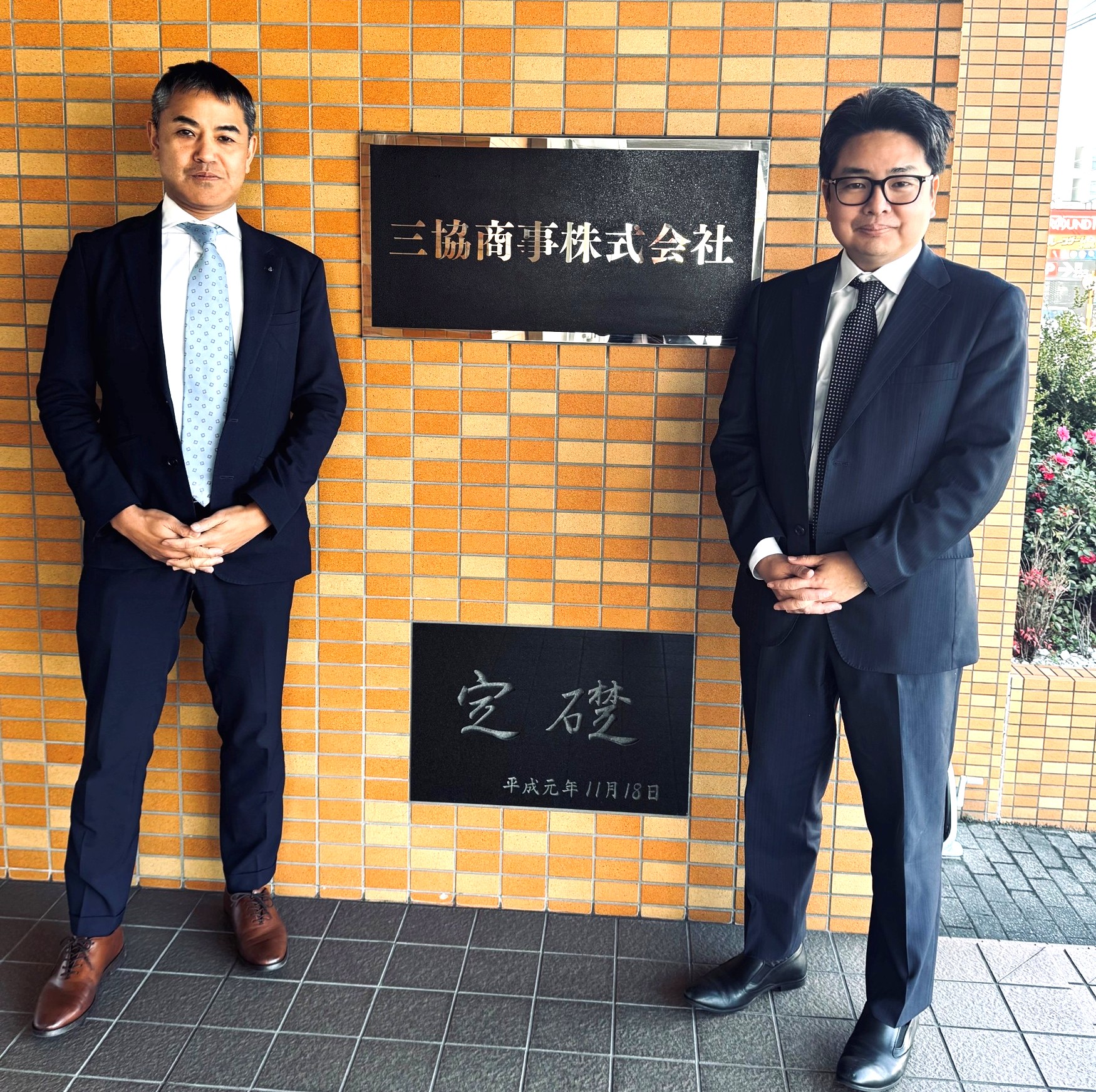 ▲会社の玄関前で。須見社長(左)と増田(右)
▲会社の玄関前で。須見社長(左)と増田(右)
須見社長は、もともと自分が経営者になるとは全く思っていなかったそうです。
須見社長「三協商事は自分の父も務めていたのですが、若いころは自分に関係があるとは思わず、私自身経営者になるなど夢に思いませんでした。一方でいつか地元に帰りたいという気持ちはあったので、大学卒業後に化学メーカーに入社したのですが、2001年に徳島へ戻り、三協商事に入社しました。」
須見社長が入社以来、担当していたのは通信事業部門。気が付けば、だんだんと経営のほうに近づく形で、2017年に社長に就任しました。
三協商事の事業は、化学品、農業資材、建設資材、通信、システム開発と幅広く、徳島本社のほか、愛媛、香川、東京、熊本の各拠点で展開しています。須見社長は一部門しか経験がないまま社長に就任したため、他の部門の話がどうしても理解しきれていないことに課題感を感じていたそうです。
須見社長「それぞれの部門の仕事を知ろうと自分なりに努力したのですが、時間的にも難しく、何をやっているのか掴み切れていないという感覚がありました。その分、業績管理は行っていたので、数字を見ながら経営をすることはやれていたと思います。数字の感覚で課題があれば、それはなぜか?と深めることもできますし、それによって就任前から収益が厳しかった部門をてこ入れして好転できた、ということもできました。ただ、そこそこ数字ができていると、なかなか突っ込みづらいのです。」
そのうちに通信事業部門の事業環境に変化が起き業績が悪化、そこにコロナ禍が追い打ちをかけます。ちょうどそのころ、小宮コンサルタンツを知り経営実践セミナーで学ぶように。コンサルタントの増田賢作とも知り合い、会社のことなどを何度か話をしていたことから、ある決心をします。
須見社長「目の前のこと(社員個々の営業スキル)を磨き上げることでなんとかこの事態に対応しようとも思ったのですが、増田さんと話していると、経営戦略や事業計画ということが出てきました。話を聴いていて、小手先を磨くよりも、この機会に会社の事業の棚卸しを行い、これからのことを考えたいと思ったのです。」
こうして、増田のご支援が始まりました。
同じ軸で可視化することで解像度が上がる。
増田「まずは、各事業部の担当の取締役や部課長に話を聴くことから始めました。そうして現状を分析してから、進め方を検討したのです。取扱商品ごとに部門を分けているので、同じお客さまの対応であっても、ワンストップでニーズに応えられていないことがあるなど、やはり部門間の連携に課題があると思いました。また、部門ごとに最適化したやり方をやっていたこともお互いの理解を阻害する原因だと考えました。そこで、まずは言語化、可視化することを目的に、共通のフォーマットを使って、部門ごとに環境分析や強み弱み分析、QPS分析等について一緒に取り組みました。」
須見社長「それまでは、本当に部門単位ですべてを行っていました。お互いが自分の業界は特別だから、と主張する状態でしたね。それがこの取り組みを始めてから、それまで、内部の言語で曖昧にして終わっていたことがすべて可視化されました。共通のフォーマットで皆が考えて言葉にしたことで、一気に色々なことの解像度が上がりました。もう一つは、よい意味での緊張感が生まれましたね。今まではなんとなく、という雰囲気で済んでいたことが、言葉として記録に残っているわけですから。」

▲会議風景
取り組みを始めて1年間、それまで曖昧だった各事業の姿、状況、課題がくっきりと見えるようになったのです。それぞれの部門で課題に対して何を行うかを決め、それを実行することをはじめました。
3カ月に1回の全体ミーティングで横の動きが活性化。
増田「2年目には、PDCAを中心に行いました。やると決めたことがやれているのかを毎月状況をヒアリングしながら確認していきます。そのうえで、3カ月に1回は全社でのミーティングを行い、各部門の進捗状況を全部門の部課長以上で共有する会を始めました。そこでは活発に、他の部門から質問が飛んだり、部門間連携の動きも出ていて同行営業が増えるなど、活発な雰囲気になっています。」
この取り組みがすぐに活きたことには、もともとの三協商事の人材や組織文化の影響もありそうです。三協商事の人や文化について須見社長に伺ってみました。
須見社長「商社ですから営業の会社です。もともと運動部出身の人が多く、活発でカラっとしている人が多いですね。ワイワイと明るい雰囲気がありますし、体が動く人が多い。地域の会社ですから、普段から私も飲みにいったり休日も一緒にゴルフをしたり、そういう関係ができています。何か問題が起きたら、部門を超えてみんなで解決しようという動きが自然にあります。そして、良いことは興味を持って取り入れることにも積極的なのです。」

▲MeatMeeting:就業後に行われる自由参加のBBQ
増田「もともと良い組織文化があったのだと思います。しかしこれまでは、情報の行き来がなく、見える形になっていなかったことで、動けなかったのでしょう。それが、一気に情報が出てきたことで活性化したように思います。もともと、事業の見える化と、部門間の連携や部門内の縦の共有、つまりタテヨコに繋がることを目指して取り組んできましたが、この良い組織文化のおかげで、取り組みが一気に加速しました。」
派手なことはないが、本来やるべきことをやると結果がついてくる。
そして取り組みを重ねて丸2年が経ち、最新の決算では嬉しいニュースが。
増田「須見社長から、この数年で最高の決算となったという知らせを頂きました。いやあ、嬉しかったですね。しっかり皆さんが動かれたことが結果につながったのだと思います。」
須見社長「今までこれほどPCDAを詰めてやったことはありません。派手なことはなにもしていないのですが、本来やるべきことをやると結果はついてくるものだと実感しました。過去も全体ミーティングは年1回ではありますが、やっていたのです。今思うと、どちらかというとやることのほうが目的でイベント的であったなと感じます。
やはり増田さんという社外の人が入って目を光らせてくれていることが効果的なのでしょうね。社内だとやっぱりどこかで言いっぱなしになり、うやむやになりがちですが、それがごまかせない(笑)。この2年間で会社の基盤が強くなったと感じます。皆が動いてくれるのも、会社が変わってきたぞ、という実感のおかげもあるように感じます。」
一段上がって見えた景色。見えてきた次の課題へ取り組み続ける。

▲BIC(Business Idea Contest):中堅社員を3チームに分けて経営層にビジネスアイデアを提言する取り組みも実施
これで万事良かった、とはならないのが経営です。ひとつの段階を上がったところで、須見社長は次の課題が見えてきたそうです。
須見社長「目先の収益のことだけでなく、中長期の事業戦略のことを考えています。主な事業フィールドである四国という人口減少の地でこれからどうしていくか。そういうことを自分は考えていかねばならないと。現状維持ではいけないし、ステージが変わっていく。会社もそういうことを考えることができる状態になっている、ということもいえます。
また、おかげさまで仕事が回っているため、現場も忙しくなってきている。管理やマネジメントの問題もクリアしながら、どう働きがいを高めていくかも考えていきたいと思います。
見通しが出てきたこともあり、絞っていた採用も再開して、新しい社員も増えています。四国にUターンだけでなくIターンする人もいます。これからは若手やこういった中途入社の社員も含めて、20代、30代を育てていきたいと思っています。
がちがちに詰めて圧をかけて動かすよりも、もっと自分たちで能動的に連携して動ける、そういう状態にしてくのが次の目標です。
そのあたりも新しい課題として、今後の取り組みについて増田さんに相談しています。全体を見ていただくために、これからは役員会議にもオブザーブしていただくことをお願いしています。」
UターンもIターンも、地元に働きたいと思う企業があればこそ。ひとつひとつステージをあげながら、四国の地で魅力的な企業を目指す三協商事の挑戦はこれからも続きます。



