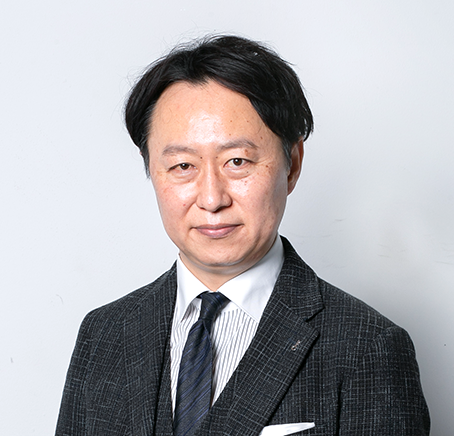―西部邁
今週の「言葉」は、西部邁(1912-1994)先生のご著書のタイトルをそのまま取り上げました。本書は108個の単語について、その語源を先生の深い教養から紐解くことで現代を見つめなおす試みによって成立している本です。108個というのは、お気づきの人もいると思われますが、仏教の「百八煩悩」に合わせただけだそうです。この108つを4つのカテゴリーに分類しているのですが、その副題が何とも正鵠を射ているのでご紹介します。
Ⅰ 経済の言葉 視野の何という狭さ
Ⅱ 社会の言葉 視線のあまりの低さ
Ⅲ 政治の言葉 視力の大いなる歪み
Ⅳ 文化の要素 視界の驚くべき暗さ
何とも、この目次だけでも自らの浅学を恥じ入るところです…。
AIに正面から抗えるはずの勤勉さ、向学心、そして真の教養を失いつつある企業人
この『昔、言葉は思想であった』を取り上げた理由はいくつかありますが、先ず経営に関わる言葉が非常に通じ合わない、ということです。またその解釈(例えばマネジメント、或いは“志”など)を同じくすることが非常に難しくなっている、ということです。西部先生の言葉を借りれば「言語的動物であるはずの人間が言語に無関心」という世相及び現象を目の当たりにすることが増えている、そう実感するのです。このことについて「「愛知」(フィロソフィ)の放棄だといってさしつかえありません」と西部先生は仰っています。哲学(フィロソフィ)の出発点はソクラテスの「無知の知」に始まります。その「無知の知」が疎んじられており、それを本書では「「愛知」(フィロソフィ)の放棄」と語っているのです。企業経営で哲学と言えば、それはほとんどの会社が掲げ存在意義ですらあるはずの理念や創業の精神を指します。ここ数年であれば“パーパス”もそうです。この真意がどうも伝わっていない、そんな状況に出くわすことがこの10年、実に多くなっているのです。仕事として、100年企業の創業者の遺訓を現代の若者のみならず経営層に至るまで講釈をさせて頂く機会もありますが、まず、「うちの会社の理念ってどういうこと?」という探求心さえないのは、企業人としての誠実さ、真摯さ(integrity)に欠けると言わざるを得ません。真剣にマネジメントをしている人には当たり前のことかもしれませんが。
マネジメント(経営)とはリベラルアーツ(liberal art)である
“Management is what tradition used to call a liberal art”「マネジメントとは伝統的な意味におけるリベラルアーツ(一般教養)である」(出典:『新しい現実』ダイヤモンド社)と喝破したのは、まさにマネジメントの父、ドラッカー先生です。また“人間学”であるとも仰っています。我々はお客さまに成果をあげて頂くために「正しい努力の積み重ね」をお願いしています。その中には人類が長い年月をかけて人間の精神を耕してきた「正しい考え方」を学んでいただく努力も含まれます。実はその学びから得られる哲学こそが、生きるうえでも経営する上でも重要な価値判断軸を体系立ててくれるのです。
西部先生の生前の予言ともとれる次の言葉をお送りして、稿を閉じます。
「現代は言葉が病む時代である、量的な多弁症のなかで質的な失語症が急速に進行するのが現代の精神状況である、と診断せざるをえないわけです。」
言葉とは人間関係において使用されるものです。言葉の本来の活力が失われることは、結局のところ、そのまま人間関係を表層的なものにとどめてしまうという精神の沈下、人間関係の崩壊に向かっていくほかありません。