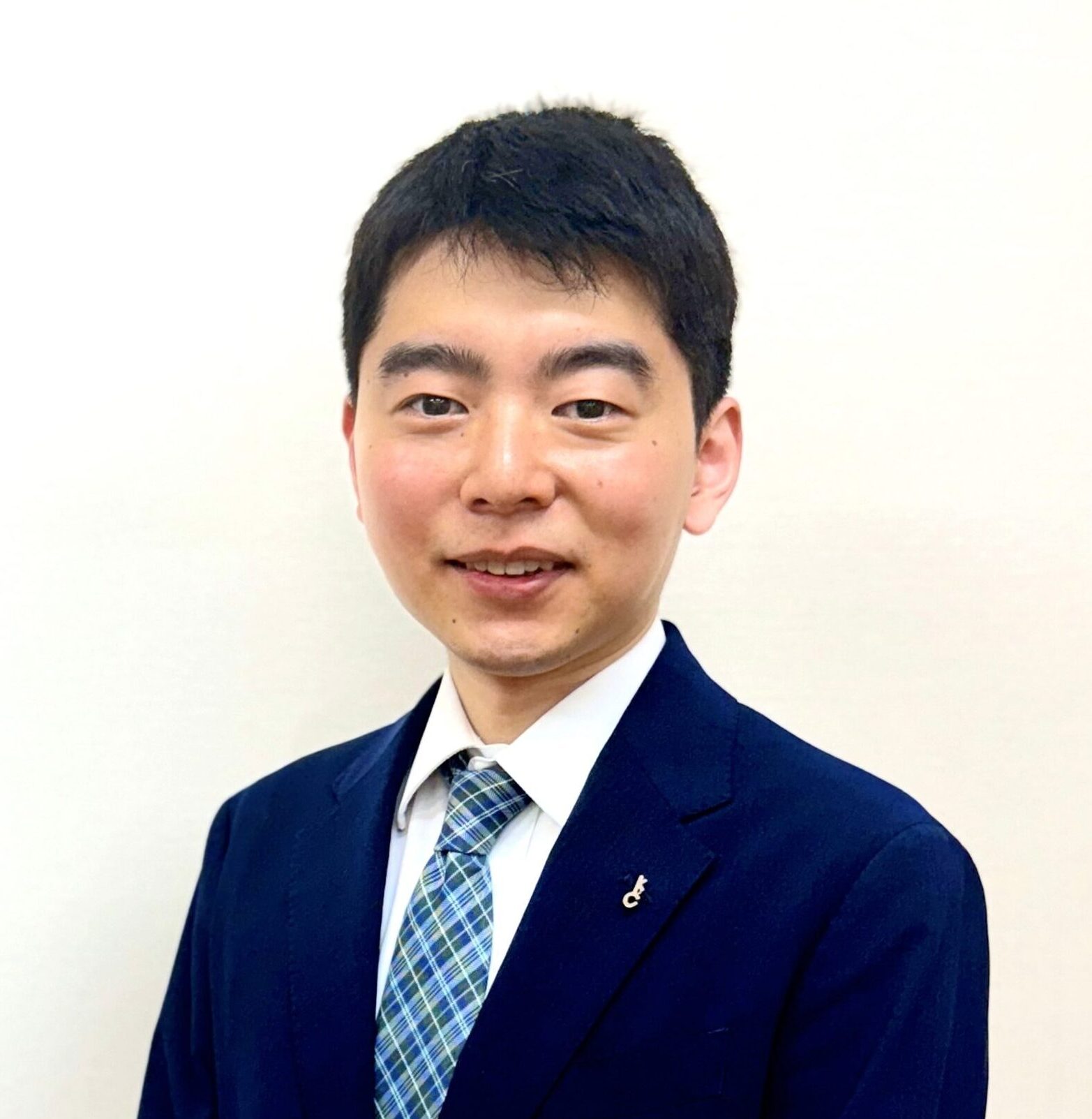本項を読んでくださっている皆さまには、仕事への向き合い方で大切にされていることがあると思います。自分が前職で働いていたトヨタ系自動車部品メーカーでは、新入社員の頃から、基本的な仕事への向き合い方やメソッドを教わりました。それらは特にメーカーや製造現場に限った話ではなく、働く上で普遍的に大切なことだと思いましたので、本項では「現地現物」という言葉についてご紹介したいと思います。
「現地現物」という言葉で一般的にイメージされるのは、「何か問題が生じた時に、机上の議論に終始せず、現場で何が起こっているかこの目でしっかりと見る」といったことではないでしょうか。もちろんその理解は正しいです。製造現場にかぎらず、あらゆる現場に直接出向き、この目で見ることで、初めて事象の本質が見えることは多々あります。その意味で「現地現物」が重要であることは論を待ちません。
しかし「現地現物」が登場するのはリアルな現場だけではなく、自分が所属した間接部門(企画部門や経理部門)でも頻繁に使われていました。ここで「現地現物」が意味するのは、「数字の裏で実際に起こっている実態をしっかり把握する」ということです。
例えば、購入している金属の価格が上昇しているのが分かったとします。その際、実際にその金属の国際的な相場は上がっているのか、相場の上昇はどうして起こっているのか、この先も続きそうか…ということまで調べられれば、それは立派な「現地現物」です。
あるいは、今月のエネルギー費が例月よりも高かったとします。その時、使用量が増えているのか単価が高くなっているのか、といった観点から明細を分析したり、使用量が増えているなら現場まで聞きに行って、その原因を深堀りするのも「現地現物」の例と言えるでしょう。
ここで大切なことは2つあると思っています。まず、数字などの情報を見て「なぜそうなっているのか」という疑問をもつことです。数字や情報自体は何も語らないので、そこに異常を感知し、深堀りするのは人間です。そして2つ目は「おそらくこうだからではないか」と自分なりの仮説をもって情報収集し事実を探る、という姿勢です。仮説ですので合うことも間違うこともあると思いますが、それを繰り返すことで、相場感や精度が上がっていくはずです。
上記のまとめとして、自分なりの解釈となりますが、「現地現物」とは単に現場に行くだけでなく、「自分の目で事実をしっかりと確かめ、なぜ生じているのかを納得・腹落ちする」ことだと思います。そのために必要なのは、①情報に接したとき「なぜそうなっているのか」と疑問を持つこと ②自分なりの仮説を持って周辺情報を集め事実を探ること だと考えます。問題発生の有無にかかわらず、普段からこのような姿勢で仕事にあたるのが「現地現物」という言葉の本質なのではないかと思うのです。