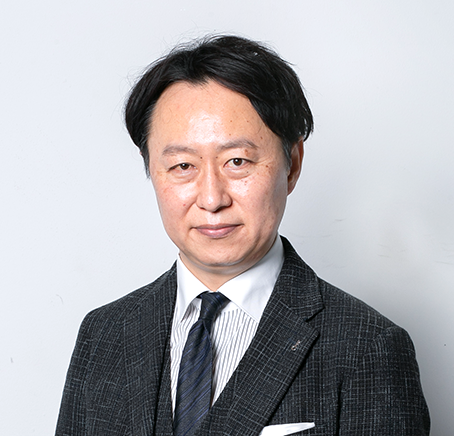◆今こそ、思いのマネジメント:MBB(Management by Belief)
今年の1月、日本を代表する世界的経営学者の野中郁次郎先生がご逝去された。野中先生の知識創造の経営との出会いは、『失敗の本質』もさることながら、本格的に学ばせて頂いたのはちょうど10年前(2015年)に出版された『MBB 「思い」のマネジメント』(東洋経済新報社)という書籍だった。有名なSECI(セキ)モデルも本書をきっかけに探求した。当時の日本企業は9割近くがMBO(目標管理制度)と成果主義を結び付けた制度を導入していた。わたしもまたその中にいた。無味乾燥な仕事の日々が続いていた時期でもあった。それまでのマネジメント経験から「何かが足りない」と問題意識を持ちながらも、組織の中で悶々としていたのでした。その「足りない」何かを明確に言語化してくれたのが、(ドラッカー先生の著作と共に)本書でした。
MBB(思いのマネジメント:マネジメント・バイ・ビリーフ)とはシンプルに言えば、高い目標値の前に、高い志(思い)がその根底にあることから始まるマネジメントである。ビリーフ(Belief)とは「思い」「信念」の意味である。詳細は是非本書を読んで頂きたい。
因みにMBBとMBOは表裏一体の関係にある。またドラッカー先生由来のMBOは正しくは“Management by Objectives and Self-control”であり、個人の主体性の発揮を目論んだものである。この点でMBBと同じである。MBBの思いの出発点は哲学にある。次のアリストテレスの言葉がMBBの目指す主体性の根源といえます。
「あらゆる行為や選択はすべて何らかの善を希求する」
(アリストテレス『ニコマコス倫理学』)
人間は本来、主体性を持った独立した個である。独立した個が一人では達成できないことを、お互いに協力し合って成し遂げるところに組織の目的、意義がある。その「個」の思いと組織の目的・目標を重ね合わせていく最初の経営行為が「方向づけ」となります。
◆「方向づけが8割」とGRPIモデル
弊社代表の小宮がよく言うように、経営とは①方向づけ、②資源の最適配分、③人を動かす、の3つに注力することです。そして企業の盛衰の8割は①方向づけにかかっている。方向づけとは平たく言えば戦略のことですが、「何をやるか、やらないか」を決めることです。従ってそこには明確な判断軸が必要となる。その軸がまさに前述MBBの「思い」であり「信念」(Belief)なのです。
いまや経営課題の解決に不可欠になった組織開発やチームビルディングの領域でよく用いられるものに「GRPIモデル」というものがある。1970年代に組織開発の先駆者のひとり、リチャード・ベックハード(Richard Beckhard)によって提唱されたもので、組織のパフォーマンスを以下のような順位(4つの基本要素)で示している。注視すべきは上から順に重要だということです。
▼GRPIモデル
G:Goals(目標):組織・チームの共通目的、ビジョン、我々にとっての成果の明確さ。メンバーが何を達成すべきかを共有しているか。
R:Roles(役割):各メンバーの役割と貢献・責任の明確さ。誰が何をするかが明確であるか。
P:Processes(プロセス):意思決定、問題解決、コミュニケーション、会議運営などの運営方法。
I:Interpersonal relationships(人間関係):チーム内の信頼関係、協働意欲、心理的安全性など。
ベックハードの提唱ののち、GEがその実践に用いて成果をあげたことから知られるようになったモデルである(あまり書籍では見かけませんが)。それゆえいくつかの研究がなされ、後年この4つの内、組織のパフォーマンスへの影響度として、最初の「Goals」が80%であるという報告もなされている。つまり、目的・ビジョン・成果目標が不明確だと、役割やプロセスがあっても組織・チームはまとまらないということです。ゆえに「方向づけが8割」の根拠ともいえるでしょう。2500年前の『孫子』も同じようなことを言っていますが…。
このモデルで注目したい点がもう一点。人間関係(関係性)は最後に位置している点です。ダニエル・キムの組織の成功循環として有名なモデルに「関係の質」⇒「思考の質」「行動の質」⇒「成果の質」というものがあります。「関係性の質」から始まるのがミソですが、その関係性の質の前提は「GRPIモデル」、つまり目的、ビジョン、我々にとっての成果(=お客さまに喜ばれること、働く仲間の幸せにつながること)が明確かどうか、メンバーが腹落ちで来ているかどうかから始まるというのが正しい解釈だといえるのではないでしょうか。そしてその軸は常にリーダーの「思い・信念」なのです。さらに会社組織で言えばそこに時間性が加わってビジョンとなります。
哲学者ハイデガーが『存在と時間』の中で語ったように、今を私たちが生きるためには「過去・現在・未来」を自分の中に持っていること。単なる歴史があるということではなくそこには未来を含めた時間の中にある存在者=人間がいること、未来は予知できないが、未来を創造するには過去・現在・未来という時間性を自分の中に持つしかない。そうした一人ひとりの集合体が組織です。ゆえに言語と習慣、そしてその集積である文化を伴った「歴史」を背負いながらその中で未来を志向していく。そうした深い未来志向の「Goals」を描きたいものです。