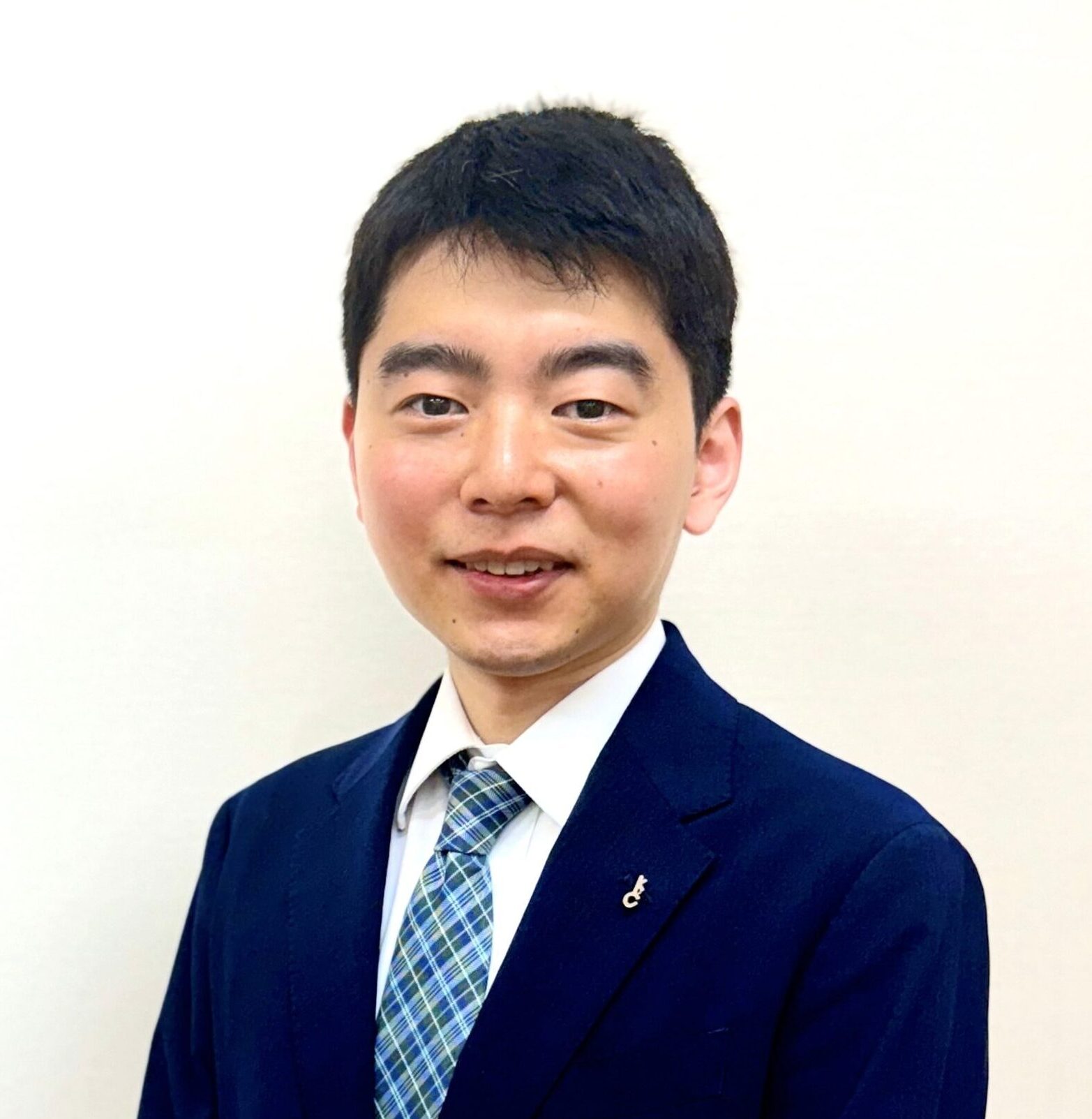私は前職のメーカーでインドに赴任していた時期がありました。勤務先の工場への行き帰りの途中には踏切があったのですが、運悪く列車が通るタイミングにかかると、通過までかなり長い時間待つ必要がありました。対面1車線ずつの狭い踏切ですが、遮断機が上がるころには、踏切の幅いっぱい2車線分にたくさんの車やバイクや人が広がり、我先に進もうとするのです。当然線路の反対側でも同じように待っていますので、踏切が開いてもお互いに進むことが出来ず、すれ違うのにも苦労し、遅々として進まないという有様です。先に行きたい気持ちはわかりますが、お互いに1列に並んだほうが、かえって早く通れたはずです。
このように、個々人が自分にとっては合理的と思われる行動をとっているのに、集団全体では好ましくない結果となることを、経済学で「合成の誤謬」といいます。諺の「木を見て森を見ず」と近いかもしれません。
マクロ経済における合成の誤謬の例をみてみましょう。たとえばある企業が自社の利益を優先し、人件費を削減したとします。当然その企業の利益は上がりますが、他の企業も同じことをすればどうなるでしょうか。働く人は従業員であるとともに消費者でもありますから、給料が下がれば購買活動も低下します。結果として、市場全体で消費が落ち込み、企業収益も悪化することになります。日本が1990年代~2000年代にかけ直面したデフレスパイラルは、こうした合成の誤謬が一つの要因ともいえるのです。
合成の誤謬は、企業内部においても起こりうることです。たとえば社内システムの構築にあたって、部署ごとに最適化された別のシステムをそれぞれ導入するとします。部署の観点で見れば、それぞれが最も使いやすいシステムですから合理的な判断です。しかし会社全体でみると、システム間の連携が取れず、別途システム間のインタフェースを構築したり、人力でデータを連携させるなどの必要が出てくるかもしれません。経営幹部など会社全体を見る立場の方は、こうした事態を防ぐため、担当部署だけでなく全社の観点からみた全体最適を考える必要があるのです。
先日の参院選では、各政党が減税や給付を訴えましたが、長期的に見れば財政の持続可能性を低下させ、将来より大きな国民負担を発生させかねません。これも目先の支持獲得のために発生した、ある意味で「合成の誤謬」といえるのではないでしょうか。民主主義国家である以上、各政党が支持率を争うのは当然のことです。そうであるがゆえに、われわれ一人ひとりが、合成の誤謬に陥っていないか、「木」も見ながら「森」も見る必要があるのではないかと考えます。
小宮 弘成